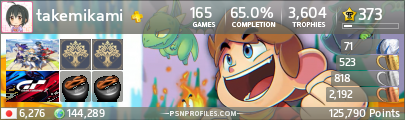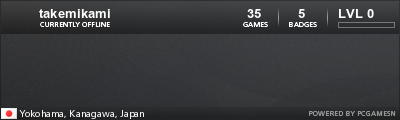手のひらの既視感
1.「夢」と「優しさ」
長い道のりだったが、随分あっという間に過ぎ去ったように思える時間。ついに僕は、一つの夢として目標としてきた教員になることができた。教員になることが夢だったとか、目標だったとか言うとなんだかとてもお堅い印象を受けるかもしれない。でも、そんなことはないと思う。自分が一人の生徒として学校に居た時間を振り返った時、その時間が非常に大切な時間で何事にも変えがたいものだったと感じるのである。だから、一人一人の生徒のそんな時間のために自分が何かできたらいい。そう思って、この夢を追いかけてきた。そして今、それを現実のものとした。これから、本当に自分のできることを探し始めるのである。
僕が勤務することになる学校。そこは自分の家からそれほど遠い距離でもなく、高校の同級生にもこの学校の卒業生が居る。それが理由なのか知らないが、学校に通い始めた時は立場は違えど、昔に戻ったような印象を受けた。近頃は制服が変わったりする学校も多いが、この学校は制服が昔のままだったのもその印象を強めたのかもしれない。ただ、教壇に立った時はやっぱり生徒の数が減っているという印象は受けた。僕が中学生の頃、学級担任が「一学級の人数をもっと減らすべきだ」といっていたような気がするが、昔は40人くらいだった一学級の人数が、今は30人強くらいで教員にとっては指導しやすくなっているのかもしれない。また、それと同じように新人の教員の数も減っている。僕は、この中学にとっては4年ぶりの新人教師だそうだ。
と言うわけで、ここでは僕に同期と呼べる人は居ない。そういうこともあって、言いたいことを言い合えるのは、大学の時の教育学部の友人たちになるのである。教育学部の友人と言っても、皆が教員になっているわけではなく、ほとんどは民間企業に就職している。むしろ、教員になったのは少数派だろう。そういった面子を集めて、卒業以来はじめてになるが、飲みにいくことになった。
「いーよなぁ、教師になれて」
そう言われて、絡まれるのが、この場での僕の仕事になっていた。教員になったのは少数派といったが、よく遊ぶ仲間の中では2人だけで、この僕と知名という男だけだった。また知名は教師といっても非常勤なので、僕は最も絡まれやすい位置にいることになる。ところでこの知名という男だが、普段他の人には自分が常勤の教員だと偽っているらしい。なんでも彼によると、この不況のご時世は公務員だと言うだけで随分と女にもてるかららしい。そんな感じの彼は随分とご機嫌な奴なのだが、教員になろうというのは本気で、教育については僕と何度も議論を交わしている。
「僕は、深い優しさをもった教員になろうと思うんだ」と僕が言えば、彼は聞いてくる。「優しさといってもどういう形の優しさを持つんだ?」。「そうだなぁ、生徒一人一人の話をきちんと聞いて、それぞれの個性を尊重して自由にさせて、失敗しそうな時や失敗した時は、立ち直れるように優しく見守ってやれるような、そんな教員かなぁ」と僕が答えると、「確かにそれはいい答えだと思う。でも個性を尊重するというのは、世の中の異端児を作ることにもなる。世の中には異端児も必要だし、いつの時代でもそのような人たちが新しい世の中を切り開いていっている。だけど、異端児になった人はかわいそうだよ、後の時代でどんなに偉人としてあがめられても、生きている時は寂しく、つらい日々を送ることになるに違いない。それと優しく見守るというのも素敵なことかもしれないが、それはつらいことでもある。自分の力で失敗を乗り越えるというのは、当人にとってとても価値のあることかもしれないが、その時当人はどれだけ苦しむだろう。その生徒が、優しく見守っている君のことを恨むことになるかもしれない。寂しいことを言うが、下手な理想を持たずに周りの教員がやるようにやっていれば、いいんだよ。子供にとっては、みんなと同じと言う状況にしてあげることが最も大切な優しさなんだよ」と言う答えが返ってきた。なるほど、真剣に生徒たちのことを考えている。だけど僕はそんな回りくどい優しさを持ち合わせる気は無かった。彼とは意見が異なるけれど、教育について様々な議論を交わしたいと思える。そんな彼との議論を通して、また僕は「優しさ」について考える。そして、それを大事にして教室に戻っていこう。
- いろんな生徒が居る、教員が居る
いろんな生徒が居る。もちろん新米の教師なので担任を持つということはないのだが、自分の担当の授業だけという短い時間だけ見ても本当にいろんな生徒が居るとは、素直な実感である。いままでに教壇に立つという経験が無かったわけではないが、実際に教員として教壇に立つといろいろなことが見えてくる。自分が学生や生徒だった頃に何らかの発表などで教壇に立った時などは、割合皆まじめに話を聞いてくれていた。が、教員となったら話は違う。生徒にしても教師にしても毎日がマンネリなのである。僕がどれほど懸命に授業を行ったとしても、寝ている生徒も居るし、手紙を交換している生徒も居る。また逆に自分が疲れていて力を抜いて授業をしている時に限って、目を輝かせて話を聞いている生徒なんかも居たりする。また、授業中には話を聞いていないように見えるにもかかわらず、授業が終わってから質問しにくる生徒なんかも居る。この生徒の質問がまた、的を得ていて、授業中にきちんと聞きなさいと叱ることができなかったりするから困ってしまう。
職員室で先輩方とこのような話をしていたりすると「君は未だ若いからねぇ、生徒たちと話があって授業もしやすいだろう」というような意見を聞く。なるほど、ちょっとした授業中の雑談で、流行歌やテレビの話題などに触れたときに、未だそんなにジェネレーションギャップというのは感じたりしない方だ。といっても、やはり中学生たちには少しついて行けていないということも感じたりする。このまま教員を続けていって年をとっていった時は、生徒たちとどのような雑談をしたらいいのだろうか。頑張って最新の流行についていって流行のわかるおじさん教師になっていくべきなんだろうか。まぁ、そんなことを今考えても仕方がないけれど、今自分を見つめた時に生徒とのコミュニケーションのとり方に、そういった流行に頼る以外の方法を見つけることができていないのも事実だと感じる。そしてふと優しさに立ち返るが、生徒一人一人の話を聞いてやれるような教員、そんな教員になろうとすると生徒とのコミュニケーションが最も大切な仕事の一つとなるのだろう。
そんなコミュニケーションのおかげか、担任をもっていない僕にもいろいろな相談を持ちかけてくる生徒たちが居る。もちろん大半の相談は授業の内容で理解できなかった部分の質問なのだが、他にも勉強の仕方について相談されることもあるし、進学のことについて聞かれることもある。もちろん、テストの平均点や通知簿の評価がどれくらいになりそうかと聞かれることもある。そこで自分が考えることなのだが、こういった生徒たちとの相談をどのように対応するかが、僕の考える「優しさ」につながっていくのだと思う。だから僕は、話かけてくる生徒たちの話は全て聞こうと思っている。もちろん授業中の私語雑談は程々にしているが、休み時間中などはできる限り話をするようにしている。そういった努力が生徒たちに伝わるのか、僕に話し掛けてくる生徒は多い。そういった僕の心がけに対して、生徒の話をあまり聞かない先輩方が多い。先ほど「君は未だ若いからねぇ」と言っていた先輩もその代表格だ。その先輩も若い頃は生徒たちと頻繁に話をしていたのだろうか。
いろんな教員が居る。いろんな生徒が居ると感じていたが、いろんな教員が居るとも感じる。そんな風に思って回りを見回してみると、意外といろんな教員が居るわけではないと思った。生徒たちを見ているといろいろな個性を見つけることができて楽しいが、振り返って教員を見てみるとそんなに個性らしいものをみつけることはできない。これが大人になるということなのだろうか、と思うことも無くはないが、それにしても画一的な人間ばかりだと思う。こんな教員たちの下では生徒たちは、個性的に育たないだろうと思うし、せっかくの個性も殺されてしまうだろう。そこでふと知名の言葉を思いだす。
「下手な理想を持たずに周りの教員がやるようにやっていれば、いいんだよ。」
知名の理屈から言えば、教員の姿というのは画一的で結構なことなのだろう。しかし僕は、生徒たちの個性を尊重してやりたいと思う。生徒一人一人の話を聞いてやることは楽しいと思う、また生徒たちが自分の好きなことや熱中していることについて、目を輝かせて話している姿を素敵だと思う。また僕は、それによって教員としてのやりがいを感じるし、そんな姿が好きだ。
- 風景を眺めるように
職員室という場所で、先輩方を話をすることは非常に勉強になり、得られることも多い。だが僕は学校内をうろうろとして生徒たちを見ることも、それと同じかそれ以上に勉強になり、得られることが多い仕事だと思っている。そういうわけで、僕はよく学校内をぶらぶらとしている。そういった時間の中でいろいろなことを知ることができる、どの生徒とどの生徒が仲が良いかといったことや、生徒たちの流行、生徒たちの学校内のたまり場など。そうやって自分の目線を生徒たちと同じ高さにしておくことが、様々な問題に対処する上で非常に有効であると感じるのである。
そんな日常の中に一つの問題を見た。これは僕が校舎の屋上で、屋上に上がってしまったテニスボールなどを回収する掃除をしていたときのことだ。僕が上っていた隣の棟の校舎の最上階の窓のガラスが割れたのである。実はその一部始終を見ていたのだが、ある生徒が、他の生徒によって窓ガラスに頭を強く打ちつけられていたのである。そしてガラスが割れたとたん、周りにいた生徒たちは蜘蛛の子を散らすようにそこから離れていった。その後僕が職員室に戻ったと同時くらいに、その生徒が頭から血を流して倒れているという報告が入った。その血を流して倒れている生徒の名を、小田君といった。この生徒は、僕が授業を受け持っているクラスの生徒でもあるので、すぐに小田君の担任の教師とその現場に向かった。現場の状況は想像以上にひどいものであり、素人の僕らには何もできず、ただ他の生徒が混乱しないように教室で待機するように指導するだけだった。
それからの時間は、僕には手の届かないところで回っていった。救急車がきて小田君を運んでいき、担任の教師は小田君の入院する病院と彼の家を行ったり来たりと忙しく、僕はというと担任の補佐と言うことで度々ホームルームの指導などを任されていた。その事件の後、担任の教師に自分の見たことの一部始終を話しておいたのだが、多忙のためかあまり話を聞いていない様子で、いつの間にか、あの事件は小田君が一人で転び窓ガラスに激突したということになっていた。そして詳しいことは、小田君が意識を取り戻し次第調査すると言うことになった。それも随分な話なので、僕は校長や教頭などに自分の見たことの一部始終を話し、ホームルームや面談などの時間を用いて生徒たちにこの問題を考えさせるようにするべきだと主張したが、小田君が回復し本来の担任が学級を見ることができるようになるまで待つように、事を荒立てないようにとの指示を受けた。確かに本来の担任では無い者がこのような問題に対応しようとすると、生徒たちが混乱する原因にもなるので適当ではない。また生徒たちが混乱してしまった場合に、新米の教員である自分に対処しきれるかというと難しいかもしれない。校長らの言うことももっともなので、生徒たちの様子を見ながらとにかく待つことにした。
待っている時間は、自分が無力だと感じざるを得ない時間だった。確かにこの問題でしばらく学校はどたばたとしていて忙しく。自分もその中でさまざまな仕事をこなした。といっても、対応のために授業をできない教員の変わりに自習プリントを配布し、その後教室内で生徒の様子を見る、というような仕事ばかりだった。もちろんそういった仕事も大切な一つだと思うのだが、事件の始終を見ていた自分としては空しい時間として流れていった。そしてしばらくすると、何も無かったかのような日々へと戻っていった。小田君の意識が戻り、担任の教員も返って来た。そして僕の行っていたホームルームの指導についても本来の担任へと引き継がれた。
「頭に怪我をした小田君についてですが、頭の包帯が取れるまではまだ三ヶ月ほどかかるようですが、予想よりも回復が早く、来月早々にも学校に戻れるそうです」と、担任の教師が発表をした時は教員は胸をなでおろし、生徒たちも良かったと感想を述べたらしい。
さて、これから担任の教師がこの問題について取り組むことになるので、僕は自分の見た一部始終を担任の教師に話した。すると「生徒たちが混乱することになるから、他でそのようなことを言わないようにして欲しい。この問題については私が対応する」との返事が返ってくる。僕は伝えるべきことは伝えたので、後は担任の教師に任せることにした。そして担任の教師がだした答えは、「友達がつまづいたりしないように、窓のそばにある掃除用具入れの整頓をきちんとして、用具入れからはみ出しているホウキなどをみつけたら気づいた人が片付ける。また、窓のそばで走り回ったりしない」というものだった。
- 手のひらの既視感
「本人が転んだといっているんだから」と、僕の話を真剣に聞いてくれる様子は無かった。担任の教師は小田君本人が転んだといっているのだからそれでよいのだの一点張りだった。また回りの教員たちも「何かの見間違いだったんだろう」というような感じで僕を見ていた。良心的な先輩は「君は教員になったと張り切っていたからねぇ、疲れていたんだろう。教員に成ってすぐに、こんな事件に巻き込まれたりしたら混乱するのも無理はないよ」と僕に声をかけてくる。もちろんはっきりと見てしまったものをそう簡単には否定できない。また、僕はその時疲れても居なかったし、見間違いとも思えなかった。
そんな納得できない思いを抱いたまま過ごしていたが、ついに小田君が学校に戻れるという日が来た。そしてクラスメートたちは暖かく彼を迎え入れたらしい。教室に戻る前に職員室に挨拶に来た彼を見たが、頭に包帯と言っていたのでどんな状態なのだろうと思っていたが、それほど大げさなものではなく頭にガーゼを当てているという程度で、帽子をかぶればわからないほどのものだった。それを見て僕も安心をした。また機会を見つけて彼と話をしてみようと思う。
「クラスメートには暖かく迎え入れられている」周りの教師たちは、病院から戻った小田君に対する印象をこのように言っている。なるほど確かに彼は明るく元気にしている。また、校内で彼の姿をみつけて声をかけたりしても、彼は笑顔で挨拶をする、まるで何事も無かったかのように。そんな彼のあまりにもわざとらしい何事も無かったかのような態度が気にかかった。「頭の怪我はもう大丈夫か?」と問うと「はい、大丈夫です」と笑顔で答える。それほど詳しくではないが、僕は以前から彼のことを知っていたが、こんなに笑顔を振り撒いているタイプの生徒ではなかったように思う。頭を打った衝撃でおかしくなったか。僕にはそうは思えない、彼の笑っている姿は何か演技を感じさせた。
そんな彼の姿を見てふと思い出す。僕が彼と同じように中学生の頃、彼と同じように学校の廊下で殴られたことがあった。僕の場合は病院に運ばれるような怪我をしたわけではないが、殴り返してやれない自分が悔しかった記憶がある。また殴られるのが恐くて、こびるように毎日を送っていたような気がする。でも、教師や両親にいじめられているのがバレると心配をかけると思って、ずっと黙っていた、そしてずっと、もっと、無理やり元気に笑うようになっていたように思う。そんな回想をすると、小田君という人物が、自分の手のひらの上に居る過去の自分の分身のように思えてきた。そしてなんとしても、彼をひそかな苦しみから救わなければならないように感じられた。
早速行動を開始しようと思う。ただ、派手に動き担任や他の教員に行動を知られると何らかの処分が行われるだろうし、結果的に全てを闇に放り込まれてしまうかもしれない。そう思った僕は「窓の傍に何か躓きやすいものがあったと考えられるので、それが何だったかを調べるために生徒たちに現場を目撃していないかどうか」について聞き込みを行うということを始めることにした。そのような形で生徒たちから情報を集めていけば、結果的に「小田君が窓に頭を打ち付けられていた」という情報を生徒たちから引き出すことができ、何らかの対応を行うことができるようになるだろう。そんな考えで僕は、いろいろな生徒と話をしていくことにした。しかしながら生徒はみな、関わることを嫌がるようにして何も知らないと答えるばかりだった。僕はというと心の中で「誰か自分が見た真実をありのままに話して欲しい」という思いを抱きながら、表向きは生徒が躓いて転ぶ可能性のある危険なものを安全に配置しなおすために頑張っている新米教師を演じていた。
そんな化かし合いのような生徒たちとのコミュニケーションをしばらく続けていたが、いいかげん僕自身もそんな毎日に疲れてきていた。いつまでたっても生徒たちは知らぬ存ぜぬを続ける。そして僕はというと、何もできていない自分の無力さに嫌気がさしてくる。そして自分が見たと思っていたことは、他の教員たちの言うように見間違いだったのではないかとさえ思ってくる。そんな自分が、自分の手のひらの上に居る過去の自分と重なるような感覚を覚える。僕は今、何をしているんだろう。
- 過ぎていった時間
随分と疲れを感じた日々だった、そこで僕はというと何もできないまま一年の歳月を過ごした。振り返ってみると本当にいろんなことのあった一年であったが、何もできなかった一年だった。そして、今も何もできないまま周りの世界だけが進んでいく感覚を抱く。「誰かに助けて欲しい」そんな思いを今、心の中に抱いている自分が居る。何もできないまま時間だけが進んでいく感覚のなかにおぼれている、そしてこの沼から誰かが引き上げてくれるのを待っている自分が居る。そんな弱気の中でふと自分の歩んできたこの一年を振り返ってみた。最も大きなこと、それは探して選ぶまでも無く小田君の事件のことである。そう、そして僕はその時、彼を助けようと思っていたはずだった。しかしながら、いったい今の自分の姿は何なんだろう。人を助けるどころか、自分が人に助けられるのを待っているなんて。
自分が教員になった意味を振り返ってみる。それは「優しさ」だった。生徒たちと彼らの個性を認めてやれる優しさを持って接することで、彼らの可能性を伸ばしてやる。そして、彼らが苦しい時やつらい時に見守ってやる優しさも持っておくこと。そう、そして僕は確かに彼を見守っていた、それだけだった。また、知名の言ったような「周りの教員がやるようにやっていれば、いいんだよ。」という優しさについても、結果的に周りの教員と同じようにしていたので、問題は無かったといえる。しかしながら感じられるこの空しさは、一体何なんだろう、「優しさ」とは一体何なんだろう。それに、人と接するということはなんて難しいことなんだろう。
これが僕の過ぎていった時間だった。僕は今こうしてここに居る、随分と回り道をしたように思えるけれど、それなりに充実した日々を送っていると思う。今の僕の毎日は、人と接しなければならないというようなことはない。一人で居たいと思えば一人で居ることも許される。そんな毎日を送っている。そう、僕は教員を続けるということをあきらめたのだ。平たく言えば逃げたことになるのだろう。これを読んでいる人たちは僕を笑えばいい。僕は今こうして、一人机の前に座りこの小説を書いているのだ。
ところで読者の中には、あれから小田君がどうなったのか気になる人も居るだろう。彼は僕とは違い、強い人間だったようだ。学年が変わった時のクラス換えを期に、いじめらしいものは無くなったようだ。彼は元気にしている。本当に心のそこから笑うようになっていった。彼は僕の手の届かないところで大きく成長していった。そう、結局僕は自分ひとりの殻の中であがいていただけで、何もできなかったのだ。それどころか、自分の問題に立ち向かうことすらできずに逃げて行ったのだ。
だけど聞いて欲しい。人が努力をするということは素晴らしいことで、いろいろな困難に打ち勝っていくことでいろんな発見ができる。人は、無限の可能性を秘めていて、努力していけばその可能性を現実のものにすることができる。それはとても素敵なことだと思う。だけどそれを現実のものにすることは、とても苦しいことで、挫折することもある、逃げたいと思うこともある。そんな時、人は逃げてもかまわないんじゃないかな。そうすれば、自分が自分で居られる。時には、そうしなければ自分が自分で居られなくなる事だってあるんだから。
そう、そしてやっと今気づいたことがある。今僕が感じていることは、まさに知名のいった「優しさ」なのだ。困難があってそれに立ち向かえる人は素晴らしい。でも、それは回りから見れば素晴らしいのであって、本人はただ苦しいだけだったりする。僕は今、教員という道から逃げ出したことで、充実した毎日を送っている。こんな感情を抱く僕が、教員として生きていくことは無理だろうね。これでは、授業を抜け出した生徒を叱る事すらできないじゃないか。