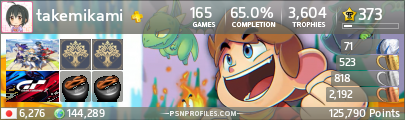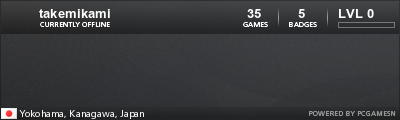狼少年の物語
1.狼と少年
少年は、誰から言われたわけでもなく、特にこれといったきっかけがあったわけでもなく、村から外れて森の中に居ることを愛するようになった。そしていつも、孤独の中にいた。そして、だんだんと寂しいという感情を覚えるようになった。しかしその時少年には、あらためて村の中に溶け込んで行こうとするだけの勇気がなかった。
少年はいつも木の上で寝ていた。しかしその日は疲れていたのか、木の根元で眠り込んでしまっていた。少年は眠りの中から、自分の傍のかすかなぬくもりを感じた。眠い目をこするようにして、目を開けた少年は、自分の傍らの暗闇の中に獣の姿を見た。それは、少年と同じくらいの大きさをした狼だった。驚いて起き上がった少年につられて、目を覚ました狼は少年の方を見た。その視線を感じた少年は恐怖におののき、村のほうへ向かって走って逃げた。そして村に近づくと、大きな声で、
「狼が出た、狼が出たぞ」
とわめいた。それを聞いた村人たちは、みな大急ぎで家の扉を閉め、災難が去るのを待った。その時、少年の姿を見つけたある村人は、扉を開けて少年の迎え入れてくれた。少年はその村人の家の窓から、外をかけていく狼の姿を見た。去っていく狼の姿を見送った後、少年は村人の家の中に視線をやった。その家には、赤いずきんの女の子と母親らしき女性が居た。少年は二人に感謝の言葉を述べようとしたが、女の子を見た時に目が合ってしまいなんだか恥ずかしかったので、母親らしき女性に、
「ありがとうございました」
という言葉だけを残して、その家を後にした。
そんなことがあってからも少年は、相変わらず森の中で過ごした。ただ以前よりも、木の上で過ごすことが多くなっていた。木の上から下の様子を眺めていると、以前よりも森の様子がよくわかるようになった。森の中に人の家を見つけた時は、森の中には人は居ないと思っていた少年にとって大きな発見だった。そしてもっと大きな発見は、たびたび赤いずきんの女の子が、その家に住むおばあさんに果物を届けにくることだった。少年が、はじめて森の中で女の子の姿を見つけた時は、不思議な気持ちだった。が、それからは女の子の姿を待ち構えるように、おばあさんの家の傍にある木の枝で過ごすことが多くなっていった。
そしてしばらくは、そんな平穏な日々が続いた。しかしある時また、木の根元で眠り込んでしまった夜があった。その日は、いつもと違う風の感じが理由なのか、真っ暗闇の中で少年は目を覚ました。そして少し離れた草むらのなかで、何かが動くのがわかった。狼だろうか、少年にそんな感覚がよぎった。そしてその動くものは、少年に向かって語りかけてきた。
「逃げ出さなくてもいいよ、僕はただ君と話をしたいだけなんだ。君はずっとこの森の中で過ごしているのかい、この森の中にはたくさんの生き物たちが居るのに、君はひとりぼっちみたいだね。実は僕もずっとひとりぼっちなんだ」
そう語ると、草むらの中から一匹の狼が現れた。少年は、その狼がかつて自分のそばで眠っていた狼と同じ狼だと感じた。そして少年は驚きを隠さなかったが、逃げると言うことはしなかった。そして、狼は少年の方に目を向けた。その視線は何とも言えない優しさと寂しさに満ちた視線だった。そしてさらに狼は少年に話を続けた。そして、少年も狼にたくさんの話をした。話し疲れた二人は、いつの間にか眠りの底に落ちていった。
そして少年が目を覚ました時、狼はまだ眠っていた。その光景は、少年が以前感じたことのある風景だったが、そこに恐怖はなかった。そればかりか、とても優しい気持ちになっていた。少年にとって、話し疲れて眠るという経験は初めてのものだった。少年は狼に目を落とし、その毛並みをなでてやった。
2.面白い遊び
少年は狼と共に森の中を徘徊するようになっていた。いつも森の中で過ごしていた少年は、もともと人間離れした運動神経を持っていたが、狼と過ごすようになってその能力にますます磨きをかけていった。少年は誰よりも早く走ることができるようになっていた。そして木の上を飛び回ることもできるようになっていった。そんな力を持つようになった少年にとって、今まで自分が過ごしてきた森は、とても小さなものになってしまった。そして、少年は毎日を退屈だと思うようになっていった。
ある日、少年は狼と思い出話をしていた。狼と少年が出会ってからそんなに長い時間がたっていたわけではないが、二人の初めての出会いは、大変印象に残るものだった。狼を見た少年は「狼が出た、狼が出たぞ」とわめき、村へ逃げていった。狼が後を追いかけたのは、ただ少年と話をしたかったからだけだというのに、少年は死にものぐるいで逃げていった。それにあの時の村人たちの、慌てようと言えばどうしようもないものだった。そんな印象深い二人の出会いを語り合いながら少年は、狼に提案をしてみた。
「最近退屈だね。どうだろう、二人が出会ったときのように『狼が出た、狼が出たぞ』とわめいて、村人たちを脅かしてみようか」
少年の提案に、狼はあまり乗り気ではなかったようだが、少年がしきりに勧めるので一度やってみようかという気分になった。そして少年と狼は、村のそばにまでやってきた。少年はあのときと同じようにわめいた。
「狼が出た、狼が出たぞ」
そして少年は村に向かって走り出す。その後を追いかけるようにして狼も走り出す。今度も少年は、その姿を見つけた村人の家に迎え入れてもらうことができた。そしてまた同じように、窓の外のかけていく狼の姿を見ていた。狼の姿が見えなくなった後に、家の中に視線をやると、ふるえて今にも泣きそうな子供の姿が目に入った。その周りで「もう、大丈夫だよ」と声をかけている大人たちも泣きそうな声をしていた。そんな光景を目の当たりにした少年は思わず笑い出しそうになったが、その家の人たちに感謝の言葉を告げて、すぐに森の中に帰っていった。
森の中で狼と再開した少年は、自分が村人の家で見た光景や村人たちが慌てていた様子などを狼に語っては、楽しそうに笑い続けた。狼にとって少年の話は面白いものではなかったが、楽しそうに話す少年の姿を見て、狼も楽しい気分になっていった。
それからというもの、少年は「狼が出た」と騒いでは村人たちを脅かして、あわてふためく村人たちを観察しては面白がっていた。また、少年や狼の行動は回を重ねるごとにエスカレートし、狼が村人の家の扉に何度も体当たりして中にいる村人を脅かしたり、狼が家の窓ガラスを割って入っていき家の中で暴れてみたり、そしてそんな光景をみた少年はその度に森の中でおなかを抱えて大笑いを続けた。狼も別に何も面白くはなかったが、少年があまりに楽しそうに笑うのでつられて一緒に笑っていた。
しかし少年は、村人たちをからかうというこの遊びも次第に退屈に思うようになっていった。少年や狼の行動は、次第に派手なものになっていったが、逆に村人たちも狼が出てきた場合の対応も手際よくできるようになっていった。つまり、村人たちがあわてふためく光景を見て面白がっていた少年にとっては、村人たちの様子はつまらないものになってきていたようだった。そこで少年は次第に、自分が狼のように村中を暴れ回ってみたいと考えるようになっていった。少年は狼のように駆け回ることに自信があったし、何よりも村人たちが自分を見てあわてふためいたとすれば、どんなに面白いだろうと考えるようになっていた。
3.満月の夜
少年は狼と話をしていた。ずっと話を続けているというわけでもなく、時々狼はどこか遠くに向かって吠えてみたり、少年は木の実をとって口に運んだりしていた。狼の遠吠えを聴いていた少年は、何となく自分もどこか遠くに向かって吠えてみようかと思い、狼のような声で遠吠えを繰り返した。少年の遠吠えに気づいた狼は、すぐそばにいる少年の遠吠えに、遠吠えで応えていた。そんな満月の夜だった。
少年と狼の遠吠えは、狼たちの遠吠えに聞こえた。そしてその遠吠えの主の姿を探すと二匹の狼の姿があった。そしてその狼たちの一匹は少年と共にいた狼、もう一匹の狼は少年の臭いの狼だった。そしてそこには少年の姿はなかった。狼はすぐに、狼の姿の少年に気づき、少年に話しかけた。
「狼の姿になったんだね、今日は満月だからね。満月の夜には、狼の姿になる人間がいるって聞いたことがあるよ。もちろん姿が狼になるだけだし、すぐに元の姿に戻ってしまうんだけどね。でも、狼の姿の君と会えるのはうれしいよ」
話しかけられた少年は、疲れたように頷いただけだった。少年は自分が狼の姿になったことは、狼の言葉を聞かなくてもわかっていた。遠吠えをした後に突然、首を絞められるような苦しさにもだえ、体中が張り裂けそうになった。頭が割れるほど痛くなり、体中の毛は逆立った。全身の先から燃えて行くような感覚を覚えたと思うと気を失った。そして気がついてみると、自分は背筋を伸ばして遠吠えを繰り返していた。そして、狼の姿がまるでずっと自分の姿であったかのように、当たり前に満月の夜空を眺め上げていた。
狼の姿をした少年は、無償に走り出したくなった。狼の姿をした自分は、自分よりも速く走れるのでは無いだろうか。そんな思いに駆られた少年は、森の中を風のように走りつづけた。狼もその後を追った。少年にとっても狼にとっても、いつもより速いスピードで景色が流れていく様に感じられた夜だった。そして二人はすぐに森の外れまでたどり着いてしまった。視界には村の景色が見えた。まだまだ、走り足りない思った少年は村の中に向かって走り出した。ただ走りたいとだけ思っていた少年だったが、村の中に入り自分の姿を見て慌てふためく村人たちの姿を見ると、調子に乗って暴れ舞ってやろうと思った。
少年は、自分が狼にさせていたように、村人の家の扉に体をぶつけたり、窓ガラスを突き破り家の中に飛び込んだりした。自分の姿に慌てる村人たちをみてただ面白がっていた少年だったが、飛び込んだ家の中であの赤いずきんの女の子の姿を目にすると、なんとも言えない気分になった。少年が女の子のほうを見ると、その女の子は少年の姿をみて確かに恐れていたが、少年はその女の子に対してなんだかやさしさのような空気を感じていた。しばらく立ち止まっていた少年だったが、ふと気づかされるようにして我に返った。そして、赤いずきんの女の子の家では少しも暴れたりせず、そのままその家から去っていった。その家を去って行く少年の感覚は、初めて赤いずきんの女の子と会った夜のような感覚だった。
その後二人は森の中に戻っていた。少年は狼に、村人たちの驚く様子がいかに面白かったかを語っていた。しかし、時々少年は、苦い感じの表情を織り交ぜながら笑っていた。少年は人間の姿に戻っていた、夜は明るくなろうとしていた。明るくなっていく夜とは対称的に少年は眠りの底に落ちていこうとしていた。狼の姿に変わるということは、少年を大変疲れさせたのだろう。眠りにつく少年の姿を見た狼は、寄り添うようにして自分も眠ろうかと思ったが、いつもと違う少年の雰囲気に違和感を覚えたのか、一人で森の奥へと消えていってしまった。
4.狼
空には満月の代わりに太陽があった、日は昇っていた。少年は取り付かれたように木の根元で眠りつづけていた。少年はなんとも言えないけだるい疲労に取り付かれていたような感じだった。時間はどんどん過ぎていった。そしてもっと太陽が高く上った頃、少年の方へ誰かが近づいてきた。狼ではなかった。その誰かは、少年が昨日出会った赤いずきんの女の子だった。
「大丈夫ですか」
女の子が少年の傍にかけより、そうたずねた。少年は眠りから覚めた意識の中で朦朧としていたので、自分の目の前にいる女の子をみて夢だと思っていた。また現に少年は、眠りの中でその赤いずきんの女の子の夢を見ていた。少年が我に帰るにはしばらくの時間がかかったように思われた。また我に返った少年は、しばらく凍り付いていた。そして少年は、驚くようにしてもう一度我に返った。その様子をみた女の子は、驚いて抱えていた果物を落としそうになった。少年は緊張した空気の中にいたが、果物を落としそうになったそんな女の子の姿を見て微笑んだ。その少年をみて女の子も笑い出す。そしていつのまにかずっと二人は笑いつづけていた。
緊張の糸も解けて、少年の取り付かれたような疲労の色も消えていた。そして二人は何気ない話をしながら森の中を歩いていく。少年は、女の子が言わなくても、その行き先がおばあさんの家であることを知っていた。そして女の子は、少年が行き先を知っていることに何の疑問も抱かなかった。女の子にとって少年との会話は、とても楽しいものだったのでそんなことまで考えていなかったようだった。
二人は森の中を歩きつづけ、おばあさんの家にたどり着いた。女の子は、おばあさんの家の扉をたたいて、おばあさんの家に入っていった。女の子が家の中に入ると、おばあさんは笑顔を見せた。そして女の子の後に続いて家に入った少年の姿をみると、おばあさんはその少年がいつも家の傍の木の上にいた少年だということに気がついた。おばあさんは既に、少年の女の子に対する好意を察していた。おばあさんは二人に気を使い、今日は疲れているから、と言って奥の部屋に入って眠ることにした。おばあさんは、横になりながら二人の話し声や笑い声を聞いていた。おばあさんは、少年のことも女の子のことも大変いとおしく思えた。
そんなことがあってから、少年と赤いずきんの女の子はたびたび森の中で会い、話をするようになっていた。しばらく少年は狼ではなく、人間らしい日々を過ごすようになっていた。しかし、少年はやはり森の中で毎日を過ごし、夜になると木の上で月を見上げていた。そんな風に月を見上げていると、ふと少年は狼のことが恋しくなった。その夜は満月だった。思い出したように少年は咆えてみた。遠くまで咆えれば、狼が気づいてくれるのではないだろうかと思った。そして遠吠えを繰り返すうちにますます狼に遭いたくなり、遠吠えを繰り返していた。そして少年はまた、狼の姿をしていた。夢中で遠吠えを繰り返す少年は、体中に感じる熱さや痛みなどを忘れていた。そして森の中に何かの物音を聞いたような気がした少年は、その姿の無い音に向かって走り出した。少年の疲労は限界に近い。しかしなぜか走りつづけていた、やめられなかった。
少年はその場所をよく知っていた。その場所は狼の姿をした少年にとっては馴染みの場所ではなかったが、少年の姿の少年にとってはよく知っている場所だった。その場所は、おばあさんの家の傍の木だった。少年はその場所から、おばあさんの家をじっと見ていた。そして満月に向かって遠吠えをした。
5.狼の姿
飛び込んだ、そんな表現が適当だった。遠吠えで夜の静寂を破った少年は、おばあさんの家の扉を突き破る音でもう一度静寂を破った。狼の遠吠えで眠りから覚めていたおばあさんは、少年のほうに視線を送った。満月はそこにくっきりと狼の姿を映し出した。その姿を見たおばあさんは、なんとなくその狼に少年の空気を感じた。もちろんその狼は少年だった。
「どうしたんだい」
おばあさんは、冷静に少年に問い掛けた。少年は何も答えなかった。変わりにおばあさんに襲い掛かってきた。おばあさんはその狼が少年だということを確信していたので、逃げることも抵抗することもしなかった。少年の行動は、理解できるものではなかったが、おばあさんはその少年の行動を理解しようとしていた。しかし少年自身にもその行動は理解できていなかった。それどころか、少年は誰かにそれをとめて欲しいとすら考えていた。それから、おばあさんの家はすぐに血の色に染まっていった。おばあさんの体は引き裂かれ、正気では見ることもできないほどになっていた。おばあさんは、悲しみとやさしさと苦痛に満ちた表情でそこに息絶えた。少年は強く頭を打たれたような感覚を覚え、その場所に立ち尽くしていた。
ずっと凍り付いていたように少年は、その場所を離れていなかった。少年はそのまま朝を迎えていた。月明かりは日差しに変わり、おばあさんの家に差し込んでいた。森の中からは、さまざまな音が聞こえていた。鳥のさえずり、小川の流れ。しかし少年の中には響かない音ばかりだった。そんな少年に遠くから人がやってくる音が聞こえてくる。少年は、その音の主が赤いずきんの女の子だと気づいた。
女の子は、すぐにおばあさんの家の傍にやってきた。開けっ放しになっている扉に違和感を覚えて、女の子は小走りに家の中に入ってくる。そこで女の子は、血まみれなって倒れているおばあさんとその向こうにいる狼の姿を見た。狼と視線を合わし少しの間固まっていたが、その瞬間の後その場にへたれこんでしまった。
少年は、赤いずきんの女の子の方へと進んでいった。女の子の傍に歩み寄りその首を咥えようとした時、少年の目の前には狼の姿があった。それは、かつて少年と行動をともにしていた狼だった。少年は言葉を失い、狼を見ていた。狼は少年に襲い掛かろうかという雰囲気だった。二人はしばらく互いの様子をうかがうような感じだった。狼は訴えかけるような目で少年を見ていたので、それを察した少年は狼の言葉を待つことにした。
「どうしてこんなことをしてしまったんだ。人は狼を恐ろしい獣だと言う、私たちは人を襲ったりはしないというのに。君のような人間が『狼は恐ろしい』というイメージを作ってしまっているんじゃないのか」
狼はそんなことを言った。その言葉に、少年は何も言葉を返さなかった。狼は少年の言葉を待っていた。それでも少年は口を開かないまま、しばらくうつむいたと思うと、ゆっくりと歩き出した。おばあさんの家の扉をくぐると少年はどこへ向かうとも無く、走り出した。
少年は涙を流していた、走っていた。そして心の中で「ありがとう」と何度も繰り返していた。寂しくてたまらないという表情もしていた。少年はずっと走りつづけた、夜になるまで走りつづけていた。そして、どこでもない場所で立ち止まった。そこで少年はただずっと遠吠えを繰り返していた。