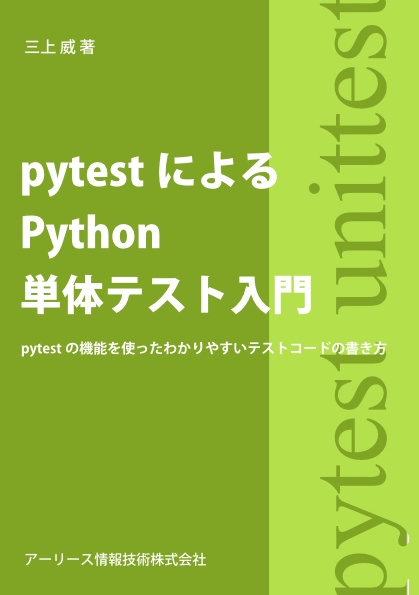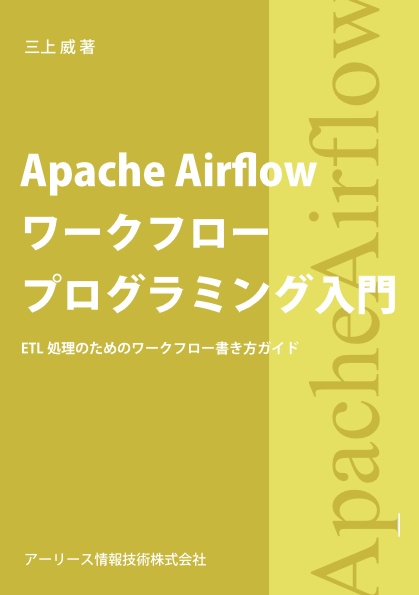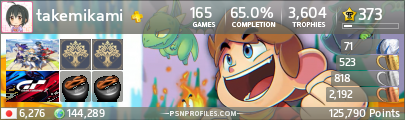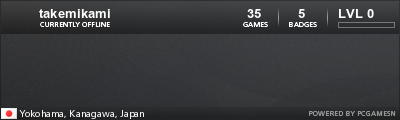このエントリは、
miエディタをアウトラインプロセッサ風に使う設定の個人的なメモです。
mi - macOS 用 日本語テキストエディタ
https://www.mimikaki.net/
以下のエントリのmi版です。
秀丸エディタをアウトラインプロセッサ風に使う設定メモ
https://takemikami.com/2022/0522-hidemaru-outline.html
公式のヘルプでは、「見出し」タブの部分に説明があります。
モード設定 - 「見出し」タブ | mi Help …
2024年から新NISAがはじまるので、
少しでも積立できるお金を増やせるように、
最近の数ヶ月は家計の見直しをしていました。
まだまだ見直しできる点はあると思われるものの、
MoneyForwardを使ってある程度は見直しできたと思うので、
そのノウハウをメモしておきます。
全体の流れは次の通りです。
準備段階
- 生活費の支払いを銀行引落・振込orクレカに寄せて1ヶ月生活する
- MoneyForwardのIDを作って、生活費の支払い口座を連携する
- 「家計簿」 …
このエントリでは、
2023年、今年買って良かったと思ったものを紹介していこうと思います。
※IT技術者っぽいものは出てきません。
ドアのすきま風ストッパー
すきま風ストッパー https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08LBPHGWZ/
ドアの下側に差し込んで使う隙間風を防ぐやつ、電気代が高くなっているので節電目的です。
ドアの近くにデスクを置いているので、足下が寒くてカーボンヒーターを使っていたのですが、
これを使うようにしてからエアコンのみでしのげるようになりました。 …
MoneyForwardクラウド会計・クラウド給与を連携していると、
給与の仕訳を作ってくれるので便利で、転記ミスを減らせて便利ですが。
社会保険料控除~年金機構への支払いの記帳で面倒な点があったのでツールを作りました。
作成したのは、
「預り金:社会保険料」と「未払費用:未払法定福利費」を、
年金機構への「未払金」にまとめる仕訳を作るツールです。
分かりにくいと思うので、順を追って説明していきます。
役員1人の法人で役員報酬のみ支払っているケースでの説明ですが、
誰かを雇用している場合でも、あまり変わらな …
この記事は、Google Apps Script Advent Calendar 2022 の12日目の記事です。
Google Apps Script Advent Calendar 2022
https://qiita.com/advent-calendar/2022/google-apps-script
Gmailの受信トレイを整理しておくとメールを探しやすくて良いのですが、
面倒なので放置してしまい、
受信トレイにメールがたまってしまいがちです。
整理作業を少しでも楽に出来ないかと思い、
このエント …
このエントリは、
秀丸エディタをアウトラインプロセッサ風に使う設定の個人的なメモです。
過去に何度もいろいろなアウトラインプロセッサを試したのですが、
使い慣れたエディタを変えることができなくて、
結局、エディタのアウトライン機能を使っています。
章立てを決めて文章を書く用途に限れば、
エディタのアウトライン機能で十分なのかなと、近頃は思っています。
そのような背景もあり、個人的な備忘録をかね、
ここでは、秀丸エディタで私が使っている設定を紹介します。
高度なアウトライン機能 | 秀丸エディタの紹 …
以下のエントリのupdateです。
Boothの売上・入金をMoneyForward確定申告・会計に記帳する手順 | takemikami.com
https://takemikami.com/2021/03/26/BoothMoneyForward.html
以前の手順ではPythonでBoothのサイトをスクレイピングしていたのですが、
Boothから「売上管理CSV」というものがダウンロード出来るようになっていたので、
これを使って、システム屋で無くても対応出来る手順をまとめました。
「Booth売上 …
この記事は、技術同人誌・商業執筆 Advent Calendar 2021 の8日目の記事です。
技術同人誌・商業執筆 Advent Calendar 2021
https://adventar.org/calendars/6410
このエントリでは、
技術書典の売上データをMoneyFoward会計にインポートするための手順をまとめておきます。
次のエントリの技術書典バージョンです。
Boothの売上・入金をMoneyForward確定申告・ …
(2022.03.04 追記)
システム屋で無くても対応出来る手順に更新しました。
Boothの売上・入金をMoneyForward確定申告・会計に記帳する手順 - 2022年版 | takemikami.com
https://takemikami.com/2022/03/04/BoothMoneyForward-2022.html
(2022.03.04 追記 ここまで)
このエントリでは、(主に未来の自分に向けて)、
Boothの売上データをMoneyFoward会計にインポートするための手順をま …
Macで作業中、照明の明るさを調整したくなった時に、
NatureRemoのスマホアプリやリモコンに持ち替えするのが面倒に思い、
メニューバーあたりからNatureRemoで操作できないかを調べたところ、
簡単にできたのでメモを残しておきます。
完成形は、以下のイメージになります。
Nature Remo Local APIを使います。
NatureRemoのホスト名を調べる
まず、NatureRemoのホスト名を調べます。
以下の通りコマンドを入力して、
出力された「Remo-XXXXXX」部分 …
機械判読可能なExcelファイルのチェックツールを作ってみたので、
このエントリで概要を説明することにします。
「機械判読可能な」と言うのは、次の総務省のお知らせにあるようなものです。
統計表における機械判読可能なデータの表記方法について | e-Stat 政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp/news/20201218
機械判読可能なデータの意味
「機械判読可能な」と言うのは、
人にとって読みやすいデータでなく、プログラムなどで処理しやすいデータを指します。
例えば、マイナ …
macOS Catalinaで、PyMC3を動かそうとしたら、
「fatal error: ‘stdio.h’ file not found.」というエラーが出たので、
調べた対処方法のメモを残しておきます。
わたしの環境:
- macOS Catalina version 10.15.7
- anaconda3-2020.02
エラーが出るまでの流れ
conda install で pymc3 をインスト−ルする。
conda install -c conda-forge pymc3 …自炊(裁断&スキャン)して書籍のPDFファイルを、
以前までは、以下の方法でサイズ縮小していたのですが。
AcrobatでPDFファイルをまとめてOCR&サイズ縮小する手順
https://takemikami.com/archives/1398/
Acrobatもサブスクになり、月額料金がかかるということもあり、
Ghostscriptでサイズ縮小をする方法に変更することにしました。
このエントリでは、その方法のメモをまとめます。
結論から言うと、次のコマンドでファイルサイズ縮小が出来ます。 …
Microsoft Officeでフォントを変更する時に出てくる、
「テーマのフォント」と言うところに、文書にあわせたフォントを指定したいと思い、
設定方法を調べたので、まとめておきます。
# macos版の設定方法になります。
# Windows版はGUIで設定出来るようなので、もっと簡単です。
「テーマのフォント」の切替方法
近頃(2020年)のMicrosoft Officeでは、
特に変更していなければ、
「テーマのフォント」は「游ゴシック」や「游明朝」になっていると思います。
これを、例えばメイ …
ソードアート・オンラインのテレビアニメに出てくるユーザインターフェイスって、
フラットデザインだよなぁ、と以前から思っていたのですが。
フラットデザインは、
(VRのような)3次元空間のユーザインターフェイスに適している、相性が良いと言う事を、
何年も前から言っていて、なかなか理解してもらえないので、
つらつら書いてみようと思います。
# 完全に素人なので、単に自分が思っていることを書くだけなのですが。
そもそもフラットでは無いデザイン、アイコンやボタンを立体的に描くデザインが
コンピュータのソフトウェアで …