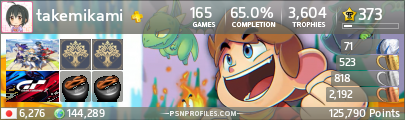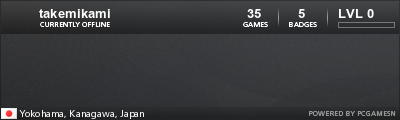メルヒェン
この本の話は全体的に見て、美しい話ばかりだったように思う。この本から、ヘッセの考えるところのメルヒェンが見えたように思う。すっかりとヘッセが好きになった。詩集は途中まで読んだけど、師が絶対的に美しいわけでなく。物語の美しさという物を、再認識したように思えた。この本全体の感想と言えば、ありきたりな言葉で、心が洗われたようだと言ったところだろうか。
「アウグスツス」…この話は、母親の子に対する愛情から出た悲劇に始まって、その子アウグスツスが最後には自分が誰からも愛されるという悲劇に気付いて、更正というか自分のした罪を認めていくことで話が終わる。読み進める内に非常に母親の愛情がもどかしかった。人から愛され過ぎて人を愛せないということが、傍目に見てこんな事なんだな。と感じた。何もアウグスツスが悪い訳じゃないんだろうな、と感じ続けていた。
「ファルドゥム」…人が山になるという発想は正に童話的だと思う。しかしこの話の中心はそこになくて、その山でありかつ男でありかつ女であることにある。山になった物がただ寂しいというのでなく、単性的である事に寂しさがあるというのは、このただの童話に見えるような話の中に、恋物語のような物が垣間見れて楽しかった。
このほかの話も非常に美しくて、心地よかった。グリム童話なんか読んでたら心が汚されるな、とも思うくらい快かった。