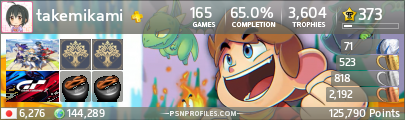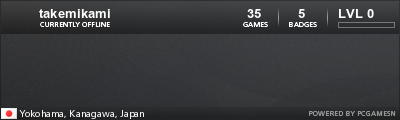やくそく
「お家に帰る途中で、公園で遊んだり、駄菓子屋さんに入ったりしてはいけません。一度お家に帰ってから、お家の人にただいまの挨拶をして、ランドセルを置いてから遊びに行きましょう」
「はーい」
何処にでもあるような、小学校の下校前「終わりの会」の風景。授業を終えた子供達は、夕方の自由な時間に向けて、この「終わりの会」で、笑い合う。
「それでは明日もまた、元気な顔で合いましょう。それでは帰りの挨拶をしましょう」
「先生さようなら、皆さんさようなら」
元気な声を響かせ合い、自由な時間に向けての子供達の会議が始まる。ランドセルを背負った小学生達は元気良く駆けながら帰っていく。ランドセルの大きさより少し小さな教科書達はガタガタという音を響かせて、このクラスの元気な男の子達は校門を出ていった。
「今日二丁目の公園で野球やるから絶対来いよ」
「わかった、じゃあ走って家に帰らないと間に合わないね」
「お前の家、遠いからな。家なんか帰らないで、そのまま来いよ」
「え、でもやっぱり先生の言ったとおりにしないと、ダメだよ」
「わかったよ、お前がイイ子なのは。とりあえず、早く来いよ」
「うん、わかった」
家が遠い僕はいつも、置いていかれたような気分になる。でも寄り道するのは良くないことだから仕方がない。だから急いで家に帰ろう。それから二丁目の公園まで行くんだ。でも家に帰る途中、二丁目の公園を横切る時。家が近くて気の早い連中は、チームを決めるためにじゃんけんをしている。遅れてくる僕はいつも、人数の少ない方のチームに強制的に決まってしまう。寂しいな、指をくわえるような気持ちで通り過ぎる。誰かがずっと、僕の後ろ髪を引いている。でも僕は、そんな事には負けない強い子なんだ。僕の意志は強いから、そんな誘惑には負けない、男の子だからね。そんな僕の強い感情を持ってしても、やはり気になってしまう笑い声達。その笑い声の中には、家に帰らずにそのまま寄り道して遊んでいる奴もいるって事を、僕は知っていた。「悪い子」と呼ばれるべき彼らは、強烈に僕の後ろ髪を引き続ける。それを振り切って、家路へと向かう僕は「良い子」であるという優越感と、「悪い子」でもいいから遊びたいという欲望の狭間に生きていた。だけど、意志の強さ。それが僕を家路へと引っ張っていった。
僕は「良い子」だよ。そんな優越感を、空虚に繰り返していた。
家に帰る途中。右と左にずっと田圃が続く道の真ん中ぐらいに、ちょっと怖いおばちゃんの居る駄菓子屋がある。その店の前を通り過ぎるときはとてものどが渇く。でもちょっと怖いおばちゃんは、その時だけちっとも怖いようなそぶりなしで、笑っている。動かすとがらがらうるさい木の扉のガラス越しに、ラムネが見える。なけなしのこづかいを、ラムネ達がひっぱていく。そんな衝動の中、「良い子」であることを忘れかけた僕は、たった今「良い子」である事の偉大性を取り戻す。だめだ、だめだ。「良い子」であることに至上の意味を見出すこの僕が、そのような陳腐な欲望に流されてはいけない。こづかいだってそんなに多くはない。こんなところで駄菓子屋の罠にはまり「悪い子」のレッテルを貼られてはいけない。そうだ、ラムネなんかうちに帰ればあるはずだ。わざわざ自分のお金を使って買う必要はない。確か日曜日にお母さんとスーパーに行ったとき、ねだったラムネが残っているはずだ。そうと決まったらまっすぐと家に帰って、ラムネを飲もう。でも待てよ。家に帰ったらすぐに二丁目の公園まで野球に行かなくちゃダメだ。早く行かないと、試合が終わってしまう。ラムネを飲んでいる暇なんてあるのか。うーん、まいったなぁ。こんな考察を続けていると前に進めないじゃないか。そうこうしている内にも野球の試合は、どんどん進んでいく。わーん。もう考えるのやめた。早く帰って、野球しに公園まで行こっと。
何しろ僕は「良い子」なんだから。
「ただいまー」って言いながら、ランドセルを置くと同時に「行って来まーす」
なんて感じで一瞬、僕は家を出た。今まで非常に様々な考察を並べ立ててきたけど、もう自由の国にたどり着いたも同然。先生の行った約束、「お家に帰る途中で、公園で遊んだり、駄菓子屋さんに入ったりしてはいけません。一度お家に帰ってから、お家の人にただいまの挨拶をして、ランドセルを置いてから遊びに行きましょう」は、きっちりと守った。今日も僕は「良い子」だった。とにかくもうそれはいい。走って行かなくちゃ。野球の試合が終わってしまう。仲間外れにするような友達は居ないけど、試合が終わってしまえばどうしても仲間外れになってしまうんだ。
僕が「良い子」だから、走らなければならない。名誉なかけっこだ。
公園の風景。そこには、男の子達の笑い声がある。みんな笑顔で、楽しそうな印象がある。夕方に近づいて、風と枯葉が舞っている景色の中で、彼らは笑顔のままで、こう語り合う。
「楽しかったな」
そこに、全力疾走しながら駆け込んだ。