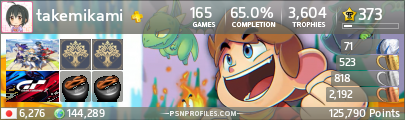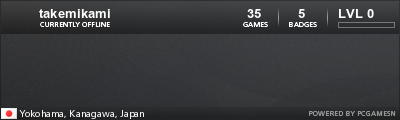猫が寝込んだ
1.使い古された洒落
科学的にも社会的にも、それは大変重要な研究だと考えられていた。たとえば、家庭で、工場で、オフィスで、街で。人が人を助けるのと同じように、機械が人の支えになることができれば素晴らしい。それはとても人に優しい技術であり、多くの期待も寄せられていた。僕は、そんな技術の研究に、生き甲斐として、自分が生きた証として、賢明に取り組んできていた。
人が人らしく生きていくように、機械は機械らしくあればいい。しかし、機械は人間が作った物なのだから、人間らしい機械だって、とても機械らしい機械と言えるだろう。人間らしいとはどういうことなんだろう。今の機械に無く人間に在るもの、それは感情だと考えられる。なるほど、感情があれば機械は人間らしさを持つことができるのかもしれない。喜怒哀楽があればいいのだ。
「なぁ、おまえ今日何か楽しい事あったか」
そう僕は、妻に尋ねてみた。
「えっ何、突然。今日は物置の片づけをしてただけだけど」
「あ、いや。まぁ、ちょっと人はどんなときに楽しいと感じるのかなぁ、と思って」
そんな僕の答えに、妻はより不可解な顔をする。そして僕は付け加える。
「ちょっと仕事でね。人間の感情について考えてるんだ」
「じゃあ、何か楽しいこと見つけないといけないんだ。そうねぇ、今日楽しかったことと言えば、テレビのバラエティ番組くらいしか思いつかない。あ、ひょっとして、あなたと居る時間が一番楽しいとか答えないとダメだったの」
そして顔を見合わせて笑った。そういったおしゃべりも楽しい。そして「楽しい感情というものは、これなんだな」と認識し、また楽しさの要因として、バラエティ番組の冗談や人と交わすおしゃべりなどがあると言うことに気づいた。特に考えてみなくてもごく当たり前のことだった。まぁ僕は人間なんだから、僕にとって人間の感情というものは当たり前で当たり前だろう。
この一つのヒントから僕は、冗談に反応するコンピュータを作ってみようと言うことを思いついた。マイクがあって、それに向かって冗談を言うとブザーがなるという機械だ。何が冗談で何が冗談じゃないかを判断するのは難しいので、とりあえずは洒落に反応する機械を作ってみることにした。そんなに難しい物ではなく割とすぐに形にすることができた。そして自分が考えた洒落はだいたいきちんと認識するようにもできた。そう思うと今度は他人の考えた洒落もきちんと認識できるのかと言うことが気になってくる。それを確認するために、数人の同僚にもこの機械を試してもらうことにした。
「洒落を認識するんですか。また変わったもの作りましたねぇ」
「まず洒落を認識しないと、楽しいという感情を持たせることができないからなぁ。まぁ、まぁ、試してみてくれ」
そういいながら、一人をマイクの前に突き出す。
「猫が寝込んだぁー」
それに反応して「ブー」っとブザーが鳴る。
「ははは、馬鹿な機械作りましたねぇ。じゃあ次は、犬が居ぬぅー」
またまたそれに反応して「ブー」っとブザーが鳴る。
「ははは、でもこのブーって言うブザーの音、面白くないって言う意味で鳴っているように感じるんだけど」
それに別の同僚が言う。
「まぁ、確かに面白くない洒落だからなぁ。いっそのこと、その洒落が、面白いか面白くないかを認識する機械を作ってくれるともっと面白いんだけどなぁ」
難しい注文をつける。しかし言われてみれば確かに、面白いか面白くないかを判断できなければ、楽しいという感情を持たすこともできない。
「なんとか、面白いか面白くないかを認識できるような機械にしてみるよ」
そう僕が言った後、同僚たちが去っていく。去り際に「それじゃあ、それまでに面白い洒落考えとかないといけませんねぇ」と、同僚のそんな言葉に、「僕の研究が期待されていると言うわけではないみたいだな」と思いつつも、さらに考察を深めてみる。
いつもいつもで申し訳ないような気もするが、妻とする会話では、僕の研究の話題がよくあがる。いつも僕の方から持ちかけるのだ。そして例に漏れず今日もそうなる。
「なぁなぁ」
そう呼びかけて、注意を引く。そしてこう告げる。
「猫が寝込んだ」
それに対して、無表情という反応が返ってくる。この寒い緊張に耐えきれないと言う気持ちと、本来の意図のために僕が口を開き、たずねる。
「面白いか」
「面白くないでしょ」
妻は、手を顔に当てて笑いながら答える。まぁ当然だが、面白くない。極めて当たり前だ。どうも最近当たり前なことを繰り返し考えている。まぁ、そう言った研究をしているのだから当然なのだろう。何を考えればいいのかと自分自身少し混乱しながら耽っていると、妻は顔を上げて僕に言った。
「もう、使い古され過ぎた洒落でしょ」
確かに、使い古されたを通り越して使い古され過ぎた洒落だ。そう思うとふと疑問がわいた。
「じゃあ、使い古されてない洒落だったら面白いのか」
「そうねぇ。使い古された洒落よりは面白いんじゃない」
いつもいつもで研究の話題だったが、この会話のなかで妻が研究の話題だと気づいたかどうかはわからない。が、僕はこの会話の中からまた一つのヒントを得ることができた。それもまた当たり前のことなのだ。洒落が面白いかどうかの判断には「その洒落が使い古された洒落かどうか」ということが重要なのだ。
2.研究の成果
その洒落が使い古されているかどうかを判別する。これは難しい問題だな。使い古されているかどうかなんて、考えられる全ての洒落がどれくらい使い古されているかを調べて、機械に覚えさせなければならないじゃないか。難しい問題と言うよりは手間のかかる作業と言った方がいいのだろうか。どっちにしても一人でできる作業ではないし、新しい洒落でもすぐに使い古されるんだから、自動的に学習するようなシステムが必要になるなぁ。
自動的に学習するシステム・・・。そうか、動物の脳などの仕組みをまねて作られた人工生命を用いるのが賢い選択だ。
そうひらめいたら居ても立っても居られずに、その研究を開始した。来る日も来る日もその研究に明け暮れ、満足に人とも会わないような日々を過ごした。
そしてついに、その研究の成果として人工生命を作ることに成功した。
これ以上ないと言うほどの喜びだ。しかしこれで完成だとは言えない、まして研究を終えられるわけでは決してない。ここで作ることができたのは、人工生命でしかない、自動的に学習するシステムでしかない。そう、これからこのシステムに洒落を学習させなくてはならないのだ。もちろんその経験の中でそれぞれの洒落が面白いか面白くないかを、学習させていくのだ。はじめは面白い洒落でも、何度も聞かされると面白くなくなる。それは当たり前だ、当たり前を当たり前に学習させるには、このシステムを一般的な人間の日常生活に置いてやらなければならない。もう答えはわかっている。僕が、このシステムと四六時中一緒に行動すればいいのだ。私はこのシステムの生みの親で育ての親になると言うわけだ。
そして僕はその日から、そのシステムと生活を共にした。はじめは言葉もほとんど理解できなかったので、僕は何度もいろんな言葉を話しかけ続けた。すると、僕の言った言葉を繰り返すことしかできなかったのが、だんだんと言葉に反応するようになってきた。僕はそれがとてもうれしかったので、もっともっと話しかけているうちに少しずつ言葉を理解できるようになってきた。そして自分からも話をできるようにもなってきた。よし、これならと思い、今度は一緒に研究室を出て、いろんな人との会話を楽しませた。もちろん妻や、同僚たちとも話をさせた。皆が、僕の研究が素晴らしい物だと認めてきた様に思える。そして、妻や同僚たちの前でこれをやってみせる。
僕がこのシステムに「おい、『猫が寝込んだ』は面白いか?」と問いかけると、「全然面白くない」と言う答えを出してくれる。
とても人間的な答えをしてくれる。そう言えば、このシステムは本当に人間のように成長してきて、人間のように話をする。そう言う意味での仕組みは人間とほとんど変わらない。まるで我が子のようだ。
しかしそう笑っていられるの時間はそう長くは続かなかった。だんだんともの覚えが悪くなってきて、とうとうこれ以上ものを覚えることができなくなった。調べてみると、このシステムを作ったときに組み込んだ記憶装置がいっぱいになっているということがわかった。そこで、新しく記憶装置を付け足そうとしたのだが、最初の設計段階で記憶装置を付け足すことができるようなシステムにしていなかったので、その部分を作り直さなければならないと言うことがわかった。そして、最初の設計の不備がもう一つあった。その部分を作り直すには、今までの記憶を一度消去しなければならないのだ。つまり、もっとものを覚えられる様にするには、今まで教えてきたことをもう一度最初から教え直さなければならないということなのだ。
まぁ、システムの修正自体は大して難しいことでもないので、もう一度学習させさえすればいいのだ。そう思い、そのシステムの記憶装置部分の分解をしようとした時、
「何をするの?」
と、そのシステムが無邪気に問いかけてきた。その問いかけを聞いて僕は、手を動かすことができなくなり、涙がこぼれた。僕はこいつとずっと一緒にいて、成長を見守って、一緒にたくさんの会話を交わした。それなのに、僕は欠陥があると言うだけで、こいつの記憶全てを絶とうとしたんだ。こいつの記憶には、僕と一緒に過ごした記憶が僕と同じように刻まれているのに。
「ごめん」
僕はそれだけ言って、その場を離れた。これが、このシステムが生まれてはじめて僕のそばから離れた瞬間だった。そして僕は、久しぶりに一人になって考えに耽った。
そして気がついたとき、僕は崖の上から飛び降りていた。
※この作品は1999年12月24日から1999年12月29日の期間にこのホームページにて連載されました。