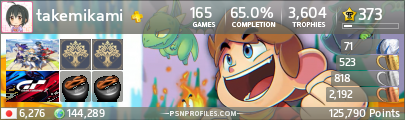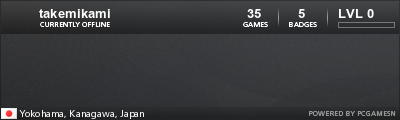最終楽章
結婚が決まった。
なんだかあっけないもので、別に大恋愛をやってきたわけではないけれど、「あぁ、こんなものか」といったような感じがした。君とは出会ったときに「あ、なんだか可愛いなっ」って感情を抱いて、それからいろんなところに誘い出しているうちに何となく惹かれあって。ごく自然な「流れ」といった感じでここまできたような気がする。別に結婚するからといって、そこまでの道のりにハードルが並べられている訳でもないんだから。そして今、ここにいる。幸せな気分というものはこんなものなのだろうか、って確認してみないと自分がどんな状況にいるのかよくわからないといった感じなのだろうか。
「これで会わなきゃいけない親戚には、一通り会ったみたいだね」
結婚するというだけで、いったい何人の親戚に会わなければいけないのか。面倒で仕方がない。そりゃあ、「結婚するんだ」って報告したい親戚もいるけど、何もほとんど話したことのないような親戚に顔を見せに行く必要はないと思うけど。家の親が親戚に対して愛想良くしているお陰で、こんな時に僕らが面倒を引き受ける羽目になるなんて、くだらない。
「これで会わなきゃいけない人は一通り終わったの?」
「うん、僕の方はね。別に会わなきゃいけないってことはないんだろうけどさ」
「そうかもね。私の方も会わなきゃいけないって人は、これ以上いないんだけど、ぜひ会って欲しい人がいるの。中学の時の担任の先生なんだけど、お世話になった先生だから、ぜひ会って私の結婚を報告したいの。せっかくだから一緒について来てよ」
「あ、わかった。こっちの方の親戚が多かったからね、断れないよ」
彼女は、会わなきゃいけない人というのに会った後は、会いたいという人に会いに行くつもりらしい。その先生とは駅前の喫茶店で待ち合わせすることになったんだけど、そこへ着くまでの十五分くらい、彼女はその先生に関する思い出話でいっぱいだった。どんな人なんだろう。僕も彼女の嬉しそうな「久しぶりに会うなぁ」という台詞で、興味を持たされていた。
カランって音をさせて、薄暗くて珈琲のにおいの立ちこめる喫茶店へ入っていった。僕は視力の低い目を細めて、左右を見回した。とそれよりも早くに、彼女はその先生を見つけた。
「あ、お久しぶりです。先生全然変わりませんね」
彼女の台詞は嘘だと思った。その先生というのは、見るからに老女といった感じだった。「十年ほど前に教師をやっていました」と言われても嘘だと思うだろう。そんな嘘の探求はともかく、彼女は嬉しそうだった。大切な人に久しぶりに会う。それが人にとってどんなに喜ばしいことか、ってありきたりな考えを回想していた。
そして彼女は僕の手を引っ張って、その先生の前に突き出すようにして席に座らせた。とりあえず、焙煎珈琲を注文した。そしてこの先生が、僕という男が「自分の教え子の婿にふさわしい男かどうかの品定め」を始めるのを待った。彼女は興奮さめやらぬ様子で、早口で先生に話しかけた。その中の会話の流れからか、その先生が僕の方を向いた。
僕は「きょとん」とした表情をしていたけれど、ふっと緊張が切れるようにして、胸が熱くなって、息苦しくなって、目の前が滲んで。悲しくなった。
僕以上に、二人の女性は困惑しているに違いなかった。
「すいません。なんだか楽しそうな再会なのに、それに水指しちゃって。二人が嬉しそうに話しているのをみていると、なんだか悲しくなって来て。彼女には、結婚相手を紹介するような大切な人がいるのに、僕にはいないんだな、って。僕には大切な友人を作る能力すらないのに、彼女を幸せにするんだって息巻いて、馬鹿みたいだな。自分一人でも上手に生きていけないのに。僕に何ができるんだろうね」
※この作品は甲南大学文化会文学研究会刊「ゲゲーベン41号」(1998)に掲載されました。