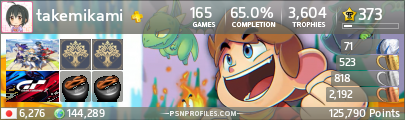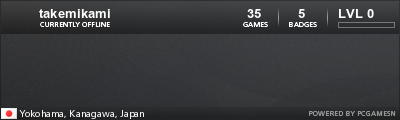夢想家
目が覚めた。べつにどおって事もない単なる朝が目の前に開けていた。そしていつも通りの退屈な僕の部屋の天井がそこにあった。天井に浮かび上がっている無機質な模様は、意味ありげで全くの無意味だった。その模様が少しくらいは僕の退屈な気分を紛らわしてくれるのではないかと、その模様の行き先を目で追っていった。その模様は言うまでもなくいつも通り、天井の中央部にある蛍光灯の方へと向かっていった。この模様を見れば医学的に見て身体によいのだろうか、などと考えてみたがそこまで考えられているとは思えなかった。だけど起きる気のしない朝の中、未だに僕は天井を見ていた。天井にある模様を見て何となく楽しい時と言うのは確かにあるけれど、今日はそんな気分ではなさそうで、そんな気分にさせてくれる天井でもなさそうだ。景色と言うには余りにも目の前にあり過ぎて面白くなく、モノクロの模様は退屈だった。いっその事この部屋の天井にステンドグラスでもはめられていて、何となく神秘的な空間が作り出されていれば楽しいのに。と考えながら瞬きをすると、そこは神秘的な空間だった。
天井にはステンドグラスが所狭しとはめ込まれていて、その上から射し込んできている光と絶妙に重なり合って何とも言えないハーモニーを、僕の部屋に響かせていた。それから何が起こったかを理解したのは、この空間の何とも言えない景色を充分に堪能した後だった。そしてそれを理解したと同時に、あらたなる期待を心に浮かべた。せっかくステンドグラスがあるのだからもっと神秘的な空間であったらいい。そう思うと教会のような風景が思い浮かんだ。しかし本当の教会はいまいち面白味に欠けるのではないかと思った僕は、教会のような空間でだだっ広く床のど真ん中に僕の寝ているベッドだけがある様な景色を想像した。そしてゆっくりと目を閉じて、また期待に踊らされている胸の鼓動の高鳴りとは逆にゆっくりと目を開いた。すると一瞬、目の前に何もなくただ広い空間をつかんだような気がした。景色と言っていいほど高い天井があった。ステンドグラスを超えて射し込んでくる光と調和した空間に居た。心地よさがそこにあって、ゆっくりと進んでいくような時間を感じた。僕はこんな空間に適合した言葉を持っていなかった。何を言えばいいのか分からなかったが、「おはよう」と言った。僕の吐いた何の変哲もない日常の言葉は、神秘的な空間に溶けていった。未だに目が覚めていない気分だった。もしまだ目が覚めていないのなら、覚めて欲しくない穏やかさだった。そして穏やかな雰囲気の流れるこの空間で、また目を閉じてみた。すると遠くの方からの足音が聞こえた。石畳の床に似合う足音が響いた。目を開いた。景色はそのままだったが僕はその空間に溶けて、この部屋からベッドというものは消えていた。そして、幻想的な衣装を着てたたずんでいた。足音はだんだんと大きくなってきた。その音は恐らくこの部屋の前と思われる場所でとぎれ、重々しい音とともに重々しいこの部屋の扉が開いていった。そしてその扉のむこうには誰も居なかった。僕はほっとした。何がなんだか分からない空間に突然落ちていって、誰かにあっても僕がどのように行動すればいいかなど分かるはずもなく。しかし今僕の居るこの空間は、素敵にこの僕を離れたくないような気分に陥れる。僕の冒険心はこの部屋に殺されて、この部屋から出ようと言う気は起きなかった。また僕の恐怖心がこの部屋から一歩でも出ることを許さなかった。僕はこの空間を楽しんでいるにも関わらず蒼白の面を下げていた。なんだか身震いをしたくなった。そう思った時身震いをしているのを感じた。それはこの僕じゃない。この部屋全体が、それともこの不思議な建物全体が。それから僕は身震いをした。しかし全く寒さなど無かった。蒼白な面を下げ続けているにも関わらず、ポタポタと自分の汗がこぼれ落ちて、床を濡らしていった。自分以上に床が濡らされていった。雨。そんな感じの空間になった。たまらなく広さを感じたはずのこの部屋は、広さではなく狭さのようなものを感じさせている。上を向いた。そこは溶けていた。雨。そう思った水滴は天井から降っていた。だんだんと雨滴は増えてきた。僕はもう上を見るのをやめて路頭に迷った。天井から降ってくる雨滴は数を増し、自分の身体から降る汗も量を増していった。けれど、寒き身体のまま蒼白な面をしていた。自分自身がそう見えた。妙に冷静な気分のまま路頭に迷い続けることにしている。天井からの雨滴は、数だけでなく大きさも大きくなってきた。床にしたたり落ちる雨滴が、僕の足下に落ちるとその跳ね返りで僕はびしょ濡れになった。そうかと思うと頭の上から雨滴をかぶり、その瞬間溺れそうになった。それから足下はもう既に、ちょっとした湖のようになっていた。そして天井は、僕のすぐ頭上にあるように感じられた。部屋がどろどろと下がってくる。そう思うと恐怖心が心を制覇した。走り出したかった。しかしこの部屋から一歩でも踏み出すのは怖かった。何もできなかった。しかし僕の足は、足だけが何者かに捕らわれたように動き出した。ゆっくりとゆっくりと扉の方へと向かっていった。ダメだ、この向こうはダメだ。そう思う僕の心をあざ笑うかのように足はゆっくりと冷静に、扉の方に向かっている。ダメだ。何がダメなのかわからない。ただこの扉の向こうが無性に怖かった。僕の心はこの洪水の部屋の中で、天井の落ちてくる部屋の中で、ぺしゃんこに溺れたがった。しかし足は強固にそれを振り払い、とうとう部屋の外に出ていった。
そして足は止まった。背中からは優しい風が吹いてくる。その風につられて振り返ったそこには、いつも通りの自分の部屋があった。風は退屈そうにカーテンを揺らしていた。
※この作品は甲南大学文化会文学研究会刊「ゲゲーベン42号」(1998)に掲載されました。