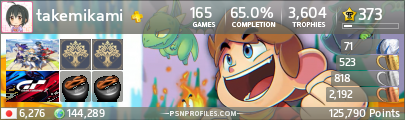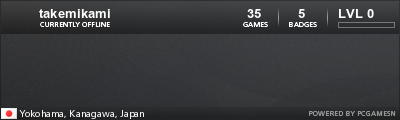河原にて雑談を
もう夏に入ろうという頃だった。その日は晴れていたので、涼しい感じのする河原へと向かっていった。それから、その河原で見たことのある顔を見かけて声をかけた。
「川中、君とはよくここで会うよな」
こんな感じに声をかけると、川中は答えた。
「川辺か、えらく汗をかいているじゃないか。そんなに暑いか」
本当に涼しそうだった。しかし僕も、そんな川中の様子と河原の涼しげな様子から少しずつ汗がひいてくるのを感じられた。それにしても川中とは、本当によくここで会う。よっぽどここが好きなのだろうか。そんな考察はともかく。僕もここから動くつもりもなかったので、他愛もない話を川中とし続けることになった。特にこれといった話題ではなく、本当に数秒後には何を話したか忘れてしまうような、どうでも良いような話題ばかりだった。例えば、友人がどうしたとか、こうしたとか、その友人にとっては迷惑なような話題とか。それから僕ら男同士二人の会話に誰が加わるといったこともなく、何となく時間が過ぎていった。もう時間は夕方になって、上流の方の橋を渡る電車に夕日が反射していた。そして僕自身少し寒いのではないかと感じるような気温になってきた。けれど、家に帰ってどうするこうするといったような用事もないので、川中と話を続けることにした。ところで、僕らの会話は多岐にわたってきたが、未だに男同士の会話にありがちな女の話には移ってはいなかった。それは僕らの周りにはまだ、河原で遊ぶ小学生達がいたからだという事は言うまでもなかった。つまり、彼ら小学生達がここから帰ってしまえば、僕らはその話に移っていくという事も言うまでもないのだ。そして言うまでもない話題へと突入したことも言うまでもないだろう。
「好きな人がいるんだけどね。いまいち、その、タイミングって物が厄介で、なんかこう上手い具合に切り出せない物だろうか。今までの経験と言っても、成功と言えるような状況があったわけでもないし、何がダメなんだろうな。そもそも、顔と身体と性格と頭と……、って言い出してもきりがないけどさ。ごめん、ごめん、これじゃあ独り言の愚痴みたいなもんだよね。それにしても、川中はもてそうだしな。僕のような男の悩みなんて分かりっこないだろうな。」
と、何が言いたいのか分かりっこないような愚痴をだらだらこぼしてみた。そんな僕の愚痴に、川中は答え始める。
「お前。女を口説くのにタイミングがどうこう言ってたらだめだぜ。一生なんて長いようで短いんだから。短い一生を楽しみたいなら、さっさとくどいちまいな。押して、押して、押しまくっていけばいいんだから。それで無理ならスパッと諦めるのもいいんだし。」
なかなかさっぱりとした意見で、そこまでさっぱりと言われると反論もしにくい。別に議論をしている訳でもないんだが。
「しかし、それは君の場合だろう。僕の場合はね、そうも行かないよ。だいたい君とは根本的に違うんだから。まず君のように女にもてないんだよ、僕は」
ますますブルーな僕の発言が続く。それにしても、そんな強烈に暗いムードを作り出す僕と同じ空間にいる川中は、そんなムードに押されることなくマイペースで自身の発言を続ける。
「紹介してやろうか、押しに弱そうな女」
この川中の発言には驚いた。だって、
「だって、君に女を紹介してもらっても、君の知り合いの女って言うのも、君と同じように、……」
その時、上流の方の橋を、ガタゴトという音と共に電車が通り過ぎていった。その電車が通り過ぎて行ってから、川中は言った。
「ごめん、聞こえなかった。水の中って言うのはよく音が伝わるからな、電車の音がそっちより響いてたみたいだ」
それって物理的に正しいのか、と言うことはさておき。そうなのだ川中は川の中にいるから。声が聞こえにくいのだ。もう一度言ってやるしか仕方がない。
「……っていうのも、君と同じように、魚だろ」
そうなのだ、川中は魚なのだ。そもそもどうして僕は魚とこんなに長い間話していたんだろう。まあ、済んだことだから仕方がない。とりあえず、ここを去ろうかと思って立ち上がりかけた時、川中が言い始めた。
「まあ、俺は魚だけど。また機会を見つけて会おう。いろいろ話したいこともあるし、いつぐらいがあいてるんだ」
まあ僕も暇だし、また話をしてみるのもいい。そう思って約束をすることにした。
「そうだね、明日の夕方。六時三〇分ぐらいにまたここに来ることにするよ」
そんな感じで約束も済ませ、いよいよ立ち去ろうとする時。川中が思い出したように言った。
「俺、時計持ってないって。そんな具体的な時間で約束されても困るんだよ」
なるほど、魚だしな。時計を持っているわけがない。そう思って僕の付けている腕時計をはずし、川中に渡そうとすると、
「おいおい、その時計重いよ。沈むじゃないか。こんな物どうやって持てっていうんだよ」
そこで僕は川中の身体に腕時計を巻いてやることにした。付け終わってから思いついたように、
「おいおい、こんなもん身体に巻かれたら泳ぎにくいじゃないか。それに身体に巻いてある腕時計をどうやって見ろってんだよ」
文句の多い奴だ。僕はもうどうでも良くなったので、諦めることにした。
「また、ここら辺歩いとくからみかけたら適当に声をかけてよ」
そんな感じの適当な口約束だけをしてその場を去ることにした。
それから、河原を去っていく途中。どうして、あんな魚と恋愛談をしたのかを考えてみたが、結論など出るわけもなかった。そのかわりと言っては何だが、どうして僕が女にもてないのかは結論が出た。あんな魚と長時間話をするような変な奴だからだ。この結論には、自分自身非常に納得できたので、たまらない充実感を感じることが出来た。そんな満足な心情のまま、家に帰っていく。背中に夕日を浴びつつ、愛しい人のことを考えながら。
※この作品は甲南大学文化会文学研究会刊「ゲゲーベン38号」(1997)に掲載されました。