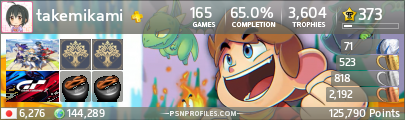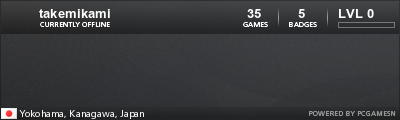死んでも誰も
「僕はいじめを受けていました。三組の二人に毎朝、殴られていました。もうこんな世の中で生きて行くのはたまりません。お父さんお母さん先立つ不孝をお許しください。さようなら。」
崖の上から飛び降りた。僕の頭の中を走馬燈のように駆け抜けていく記憶は、もう自分が目を背けた現実で、死んでいく自分の先に想いを馳せていた。僕にとって、急降下と呼ばれる現象は、ゆっくりとゆっくりと、時計の針が一秒々々を刻むよりもゆっくりと進んでいく。僕の目に飛び込んでくるアスファルトが、はっきりと見える。ここは「いじめ」からの脱出口。それが疑いようもない事実に見えて、僕は思いっきりアスファルトに飛び込んだ。
一瞬の衝撃とともに、僕の気持ちは軽くなっていった。
「やったあ、これでもう僕はいじめられることはない。やったあ、やったあ。」
この世から去ることができた。そして僕はついにゆとりと自由を手に入れた。ここにある僕の骸は、あまりにも醜い物だった。しかし、そんなことはどうだっていい。これは、いじめにあって逃げ出した僕の殻だ。今ここに居る僕じゃないんだ。僕はいよいよ、いじめられた殻から解放されて行く。そして僕は、宙に浮いている、そして眼下には僕の学校が見下ろせた。もちろんそこに僕の姿はなかった。三組の二人が僕をいじめようと待ち構えている。いつまで待っても僕はそこへは行かないのに。ざまあみろ、僕はもう自由なんだ、誰も僕をいじめられやしない。死後の数時間はそんなことを考えるのに夢中だった。愉快で愉快でたまらなかった。
何時間たっただろう。学校をサボることなんかなかった僕が居ないことに、先生がおかしく思い、家に連絡を入れたようだ。けど僕の母さんは、僕を探そうともしない。どうせすぐに帰ってくるだろう、そんな風にでも思っているんだろうな。何の関心も持たずに家事に追われている母さんを見ても、僕には「ごめん」と謝るセリフなんかでてこない。だけどこれだけは伝えたいんだ。
「もう僕は二度と帰らないんだよ。」
もう夜がやって来た。机の上の遺言状を読んだ父さんが、うろたえている。あんな表情を見たことはなかった。あんな表情見たくなかった。
「ごめん、お父さん。でも僕は勇気を振り絞って、こんなに頑張って、死を決断したんだよ。」
明朝には、学校は僕の話題で持ちきりになっていた。僕の名前も顔も知らないくせに悲しんでいる振りをしている、そんな顔ばかり見える。三組の二人もそんな振りをしている。
「お前達がいじめの犯人だってことはすぐにわかるんだ。そんな演技をしたって無駄なんだよ。」
そんなことを考えてみた。あの二人が僕をいじめていたとき、きっとこんな気持ちで楽しそうにいじめていたんだろう。今では立場が逆転した、死ねばこんなに愉快になるのなら、もっともっと早くに死んでいれば良かった。
何日も過ぎていった。僕の死はマスコミでも騒がれた、僕はあっという間に有名人になった。そして世間ではこんな風に言われている。
「死んでしまってはすべてが終わってしまうから、辛くても苦しくても生きていくことが大事なんだ。自ら命を絶つのは悪いことなんだよ。」
「ち、ちょっと待ってよ、どうしてなんだ。僕は勇気を振り絞って、こんなに頑張って死を決断したんだよ。なのにどうしてだれも誉めてくれないんだ、そればかりかまだ僕をいじめるのか。どうしてみんなは、僕をいじめたがるんだ。どうしてそんなにいじめたがるんだ。」
※この作品は甲南大学文化会文学研究会刊「ゲゲーベン37号」(1997)に掲載されました。