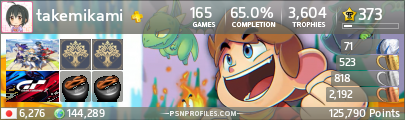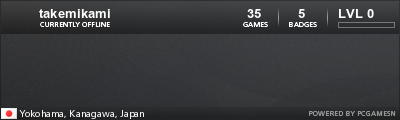奇術師の館
1.奇術への誘い
「なぁに、ちょっとしたアトラクションですよ」
そんな説明を受けた。誰がどう聞いたっておかしな話だった。僕、浩一郎は、友人達、恵太・祥子・冷子とドライブに来ていた。恥ずかしい話だが途中で道に迷って寂れた洋館にたどり着いたのだ。まさか人は居ないだろうとは思ったが、もしも人が居たら道を尋ねようと思って洋館のドアを叩いた。すると、その古ぼけた洋館の扉がすぅっと開いて、そこに立っていた老人がこう説明したわけだ。なんでも、この洋館には奇術師が居て様々な奇術を見せてくれると言うのだ。そしてその奇術の世界を体験してもらった後で、あなた方がした経験に見合うだけのお金を寄付して行ってくれればそれで結構だと言うことらしい。何ともおかしな話だった。誰がこんな所にくるというのだ。そんな商売をしていて採算がとれるわけがない。詐欺にしてもおかしな話だ。何かの宗教じゃないのかとも思ったが、冷子がいやに乗り気で絶対に体験して帰りたいというのだ。まぁいいか。そんな感じで僕もこのアトラクションというものを体験することになった。
大きな屋敷だった。奇術師から直々にアトラクションについての説明があるらしい。部屋の照明が一気に明るくなり、その正面には赤い絨毯のひかれた階段があった。ここは吹き抜けの玄関だったらしい。階段を上った先には、白いマントを羽織った「いかにも」という奇術師の姿があった。
「ようこそ、奇術の館へ。今日、みなさんには私の奇術の世界で楽しんでいただきましょう」
そう言うと、奇術師は得意げに指を鳴らした。そうするとあたりは暗闇の世界になった。するとすぐに、また奇術師が指を鳴らす音が聞こえた。奇術師の爪には灯火がともっていた。神秘的な光景だった。
「まずは手始めにちょっとした奇跡をお目に入れました」
奇術師はそう言うと、手を振り、爪の灯火を消した。今度はゆっくりと、館の明かりがついた。神秘的な光景にしばらくきょとんとしていた僕たちだったが、思い出したように拍手を送った。恵太が小さな声で「結構面白いかもしれないな」と言っているのが聞こえた。僕も内心、期待などはしていなかったが、期待した以上に面白いものが見られるのではないかという期待感を持った。そうしているうちに、奇術師は一礼し、ふっと階段の手すりの上に飛び上がった。
「ありがとうございます。わざわざこの館までお越しいただいたみなさんには、ただ見るだけの奇術ではなく、奇術の世界に参加していただきましょう」
そういうと、奇術師はマントの中から水晶玉を取り出した。
「これから、私はこの水晶玉に魔法をかけます。この水晶玉はいつでもみなさんの目の見えるところにあるでしょう。しかしみなさんはこれを決して手にすることはできないでしょう。みなさんはこの水晶玉を手にするために最大の努力をして下さい。みなさんが諦めたところで、私の奇術の世界の幕を閉じましょう。いいですか?みなさんが諦めたところで終わりですよ。なぜならみなさんは決してこの水晶玉を手にすることはできないからです」
なるほど、そういう言われ方をすると絶対に、その水晶玉を手にしてこのゲームを終わらせてやろうではないか。そんな気になる。もちろん、挑戦者がそういう気持ちになるようにこの挑発がなされているのだろうが。
「それでは、みなさん。どうぞ奇術の世界へ」
さて、いよいよその奇術の世界とやらに、入っていくときが来たようだ。始めはあまり乗り気ではなかった僕だが、このかけ声の時にはすっかりと乗り気になってしまっていたようだ。そして僕たちは進んでいく。奇術師の誘う、その奥へと。
2.せり上がる壁
入り口からまっすぐと階段を上り、奇術師の進んでいった右側の廊下へと進んでいく。しかし奇術師の姿はもう見えなくなっていた。
「おいおい、さっきの奇術師さんはどこかに消えちゃったよ。どこに行けばいいんだよ」
とは、恵太の発言。僕も同じくそんなことを考えていた。おそらくみんなそうなんだろう。という僕らの思いに対する答えだろうか。突然目の前の床から、ズズッと言う音を立てて壁がせり上がってきたのだ。僕なんかはもう少しで正面衝突するところだった。と思っていたら、お隣でガツンという音が聞こえた。祥子は思いっきり額をぶつけてしまったようだ。
「これは、奇術じゃ無くっていたずらかなぁ」
と、二人で顔を見合わせていた。
「これはここの扉には入れという事じゃないのか?」
そんな恵太の声が聞こえた。振り返ると確かにそこには扉があった。なるほど、このせり上がってきた壁は、奇術師さん流の道案内というわけらしい。それでは進ませてもらいましょうか、その部屋へ。
両開きの大きな扉ではあったが、そっと片方の扉を押し開けてみた。きっと神秘的な空間が目の前に広がるのだろうと言う期待とは裏腹に、その部屋はなんとビリヤード場だった。といっても、広い大きな部屋の真ん中に一つビリヤードの台があるだけの、お金持ちだけが持つであろう贅沢な部屋だった。
「こんな部屋が自分の家にあったらいいのになぁ」
と、恵太は感想を漏らしていた。僕も全く同じ感想を抱いた。どうせなら少しくらいビリヤードを楽しんでいっても構わないかと思い部屋を見渡したが、そこにあるのは台だけで他の道具は何一つ無かった。そうこうしているうちに、いつの間にか目の前のビリヤード台に先ほどの水晶玉が置かれていた。
ここでやっと、奇術師の奇術を見せてもらえるというわけだろうか。この水晶玉に手を伸ばしても、手にすることができないというわけなのだろう。そう思っているうちに、冷子はもう水晶玉の方へ手を伸ばしていた。するとどうだろうか、手に触れようかという瞬間、水晶玉はすぅーっと移動して、手に触れることができなかったのだ。
「あれぇ」
逆側に回って、また同じように手を伸ばす。するとまた、すぅーと水晶玉は移動してしまうのだ。
「お前がとろいから取れないんじゃないのか」
と、恵太も手を伸ばす。しかし彼もまた、どんなに素早く手を伸ばしても、その水晶玉を手にすることはできなかった。もちろん、僕がやっても、祥子がやっても同じ事の繰り返しだった。
「これって端っこに追い込んで、落としちゃえばいいんじゃない?」
なるほど、冷子の言うようにやってみる価値はあるかも知れない。そう思って、端っこに追い込むようにしてその水晶玉を移動させて見ると、思った通り穴に落ちていった。しかし、この台はふつうのビリヤードの台のように玉が落ちてくる訳ではなく、また台の中央から、水晶玉が浮かびあがってきた。
「うーん、これはいったいどうすればいいんだろうねぇ」
みんなは顔を見合わせていた。で、僕はというと、どのようにして水晶玉が動いているのかという仕組みを知ろうと賢明に観察を続けていた。手を近づけると、すぅーと水晶玉が離れていく。何故手を近づけると動くのかと言うことはさておき、よく観察しているとこの水晶玉が転がるように動くのではなく、同じ方向のまますぅーっと、地面に水平にという言い方でいいのだろうか、動いているのだ。しかしそれがわかったからと言ってどうすることもできないままだった。
3.ビリヤード場
そうこうするうちに、ふと思ったのだが、手を近づけると離れると言うことは、手以外の物を近づけるとどうなのだろうかと思い、上着を脱いで水晶玉にかざしてみた。しかしそれでも水晶玉は、同じように遠ざかっていく。なるほど、では次は遠くから息を吹きかけてみよう。そう思って息を吹きかけるとやはり水晶玉は離れていくのだ。
後は、やるとしたらどんなことができるだろうか。そう考えてみると、まだ遠くから物を投げてぶつけると言うことを試していないことに気がついた。何にしろここはビリヤード場なのだから物をぶつけると言うことは基本中の基本かもしれない。そして、ポケットの中を探ると携帯電話があった。そこで、その携帯電話をビリヤードの玉同士をぶつけるようにその水晶玉をめがけてぶつけてみた。しかし、やはりというか、その水晶玉は携帯電話からも逃げるように離れていった。
そうこうするうちにふと思ったのだが、この水晶玉の周りに囲いを作ってその囲いをだんだんと狭めていったら、この水晶玉は動けなくなって、手にすることも可能なのではないのだろうか。先ほどからいろいろと試してはいるが、水晶玉は常に平面上でしか動いていないのだから、囲いを作ったらその囲いから外に飛び越える事はないのではないのだろうか。とりあえず何かで囲いを作ってみよう。
「ちょっと、みんな上着を脱いでくれないか」
そう言ってみんなの上着を集めてみた。そして水晶玉の周りに囲いを作った。それから少しずつ少しずつその囲いを小さくしていった。すると水晶玉は、その囲いが狭まるのに反応して、敏感に移動を続けていたが、囲いの中から出ていくことはなかった。どうやら成功らしい。
「あぁ、何だそんなことでいいのか。簡単な謎だったわけだな」
とは恵太の感想だった。みんな「なんだ、それだけのことだったのか」というような顔をしている。
この調子で囲いを狭めていけばいずれ、身動きがとれなくなる。そうすれば手にすることができる。その調子で僕は台の中央に水晶玉を追い込んでいった。そしてもう少しで水晶玉の身動きがとれなくなるであろうそのとき、水晶玉は、先ほどその玉が現れた位置から沈み込み消えていった。
これはどういうことだろう。やはりこの奇術を解く答えは、そんなに簡単なことではなかったのだろうか。また別の所から、水晶玉が現れるのだろう。なぁに、そうくるのならば、今度はその水晶玉の出現パターンを分析していけばいいだろう。そんなことを考えながら、奇術師の次の出方を待った。
バタッ。
そんな音がして、入ってきた方とは逆側の扉が開いた。これはどういったことだろう。まさかこの部屋の奇術という物はこれだけで終わりだったのだろうか。まぁ、ドアが開いたのだから、進めということなのだろう。なんだか物足りないような感じはしたが、とにかく先へ進むことにしよう。
「つぎは何なんだろう」
なんだか妙に楽しそうにしながら冷子がついてくる。その後に、みんなもついてきている。
その扉を抜けると、古ぼけた階段があった。周りを見回しても他には何も見あたらない。この階段を上れということなのだろう。そして、僕がその階段に足をのせると、足下が少し揺れた。階段の一部が割れているようだ。今までのきれいな廊下や部屋とは正反対の印象だ。
「おいおい、この階段上っても大丈夫なのか」
僕と同じ感想を恵太が漏らす。まぁ、大丈夫だろう。そう思って僕は先へ先へと上っていった。不安そうな愚痴を漏らしながらみんなもついてくる。階段を上りながら、上を見上げていたが、これでもかと言うほどおんぼろな景色が広がっていた。天井を見上げると雨漏りの跡であろう黒っぽいシミが所々についている。壁と天井の間には蜘蛛の巣も張っている。階段を上りきってみてみると、天井のシミが雨漏りのシミであることを証明するかのように、それぞれのシミの真下の床に同じ様なシミが残っている。
「何ここは、汚いなぁ」
後から上りついた祥子は、いやそうな顔をして周りを見回す。
「次はあの扉をくぐれって事じゃない」
祥子の後ろから、冷子が言う。冷子は、この汚い空間を特に不快には思っていないようだ。どんどん前向きに進んでいく。僕も負けないようにその扉に向かって進んでいった。
4.汚い部屋
その扉を開けると、そこはやはりといえばいいのか、汚い部屋だった。何年も人が入っていないのだろう。床にはほこりが積もっていた。でも照明はきちんとついているんだ。なんだかとても違和感がある。歩けば足形が残るほどほこりが積もっているのに、照明は取り替えられたばかりかのように明るい。一体どうやってこの照明は取り替えられたのだろうか。実はそれが奇術なのではないか、とも思いながら部屋の奥を見るとまた扉があった。そしてその扉を見てみると、その扉には例の水晶玉がかけられている。今度はどんな奇術を見せてくれるのだろう。そんなことを思いながら、その水晶玉のかけられている扉に向かって進んでいく。しかし部屋の半分を過ぎた頃になると、急にその水晶玉は姿を消した。
「あれ、またこの水晶玉は逃げ回るのか」
そんな恵太の感想だった。その恵太のせりふがはかれる前に僕は辺りを見回していた。きっとどこか別の所に移動しているのだろう。そしてまた、その逃げ回る水晶玉を追いかけなければいけないのだろう。そう思って、僕の目があたりを探っていた。しかし僕の目にも、他の誰の目にも水晶玉の姿はなかった。その代わりといっては何だが、入ってきた方の扉の上に何か機械をつけてあるのが見えた。僕はその機械に近づいていった。そしてその機械が何かを確かめようとした。
「それプロジェクターじゃないのか」
僕が確かめるより早く、恵太が言った。
「やっぱりそうか、何となくそんな気がしたんだ」
そんな風に言いながら、プロジェクターを見上げた。
「奇術師さんは、このプロジェクターで水晶玉の絵を映していただけなのか。なんか人を馬鹿にしているなぁ」
なんだか馬鹿らしくなってきたので帰ろうかという気分になってきた。そう思ってみんなの顔を見渡した。みんな同じ様な顔つきをしている。多分みんなこのくだらない奇術にあきれて帰ろうという気分になったのだろう。首を縦に頷いた後で、僕は入ってきた扉に向かって足を進めた。みんなもついてくる雰囲気だ。そのとき僕たちの歩みを止めるかのように、バタン、バタン、と続けて二度大きな音を立てて今入って来た扉が閉まり、その後水晶玉が映し出されていた逆側の扉が開いた。どうやら、僕らをまだ引き留めるつもりらしい。振り返るとみんなきょとんとした顔をしていたが、すぐにあの奇術師の意図をくみ取ったようだった。
「仕方がないなぁ。先に進もうか」
そんな風に言ったの冷子だ。みんなまた顔を見合わせたが、まぁここまで来たから最後までつきあってあげようか、という感じで先に進むことになった。そうしてその扉を抜けると、今度は廊下に出てきた。今度はうってかわって非常にきれいな廊下だ。下の階の廊下と同じようにきれいな廊下で、きれいな赤の絨毯がひいてある。今の部屋で僕らの靴は誇りまみれになっていたので、この絨毯の上を歩くのは気が引けたが、祥子がそんなことは気にせずどんどん進んでいこうとするので、僕らもつられてそのままその絨毯を汚すことにした。
さて、どちらに進めばいいのだろうか。そう思って左右を見渡してみたが、言うまでもなく右に進むしかないようだった。左側はすぐに突き当たりだった。まさかこの左側の壁に隠し扉とかがあったりすることはないだろうなぁとか、考えたりもしたが、みんな暗黙の了解のように右の方へ進んでいっているので、僕もそれについて廊下を進んでいくことにした。また長い廊下だった。向こうの方を見てみると、その廊下はとぎれているように見える。始めはその場所で廊下が折れ曲がっているのかと思っていたが、近づいていくうちにそこで確かに廊下はとぎれていた。そこにはぽっかりと穴が開いていた。見下ろしてみるとそこには、僕らが入ってきた入り口が見えた。どうやら僕らは周り回って、入り口の真上まで戻ってきたようだ。そしてまた目の前を見ると、そこには先ほどの奇術師の姿があった。奇術師はぽっかりと空いた穴の向こう側にある廊下の続きの部分に立っているようだった。そしてここから奇術師の立っている向こう側までには、一本のロープが張られていた。
5.ロープ
そのロープの向こうに立つ奇術師は、その手に水晶玉を持っていた。一体どういうつもりなのだろう。今から、この奇術師は綱渡りの芸でも見せてくれると言うのだろうか。こうなってくると、奇術というかただのサーカスじゃないのだろうか。まぁ、始めにご老人がアトラクションだとか言ってたからそんなものなのかもしれないけど。そんなことを考えていると、奇術師がこう言った。
「それでは、みなさんにはこのロープをわたって、ここまで来ていただきましょう」
あれ、それはどういうことなのだろう。綱渡りをするのは僕たちということなのか。奇術師は何も奇術とやらを見せてくれない訳か。なんだかもうこの奇術師に期待するのが馬鹿らしくなってきた。しかし綱渡りをしろといわれても、素人がいきなりやって成功する物でもないだろうしなぁ。そんなことを考えながらもう一度その穴から入り口の方を見下ろしてみた。上がってきた階段の数から考えてもここは三階のようだ。この高さから落ちるとやばいかなぁ。そんな風に下を見下ろしていると、後ろから冷子が言う。
「綱渡りやらないの」
全くの人ごとである。自分は全くやる気がないのに、他人がやるのは当然だと思っているようだ。素人がいきなり綱渡りなんてしてもうまくいくわけがないだろう、だいたい失敗して落ちたらどうするんだ、と言おうと思ったが、なんだか面倒くさくなった。できなくもないかなぁ、そんな風に思ってきて綱渡りをすることにした。まぁ、落ちても何とかなるだろう。何がそんな気にさせたのかはよくわからないが、割と気楽に考えて挑戦する気になっていた。
「おいおい、本気でやるのか」
そんな風な恵太の声も聞こえたが、僕はもう第一歩を踏み出していた。踏み出した第一歩はふっと、落ちていくような感じでロープに受け止められて、ふわふわとした感触だった。とても解放された感じがしたと同時に、宙に投げ出されてつかむことのできない不安がよぎってくる。でも、不思議と怖くはなかった。何となく向こうまでたどり着けそうな気がした。片足を上げる。逆の足だけで支える。足を前に出す。今度は逆の足。そんな地上では当たり前のことをゆっくりと繰り返す。景色が揺れる。ゆっくりとしたリズムで。すべての時間がゆっくりと流れて、周りの空間だけは僕の気持ちをせかす。それを否定するようにゆっくりとしたリズムで歩みを進める。体中を包む不安は、開放感をくれる。
ちょうどロープの真ん中のあたりまで来ただろうか。ピンと張られたロープだとは言えやはり揺れが大きくなってきているように思われる。後ろの方では、がんばれ、と励ましの声が聞こえる。半分まで来たという達成感もあって、僕は少し得意げになっていた。爽快な気持ちも抱えて、相変わらずのリズムが僕を進めていく。そんなときにそのリズムを乱すような不協和音が重なってきた。後ろの方にいるみんなが騒がしい。足下には小刻みなリズムが流れる。得意げな気分から我に返り、前を見る。するとどうだろうか。事もあろうか、目の前にいる奇術師がナイフを取り出し、ロープにこすりつけているではないか。このままではこのロープは切られてしまう。僕は焦った。しかし焦ることもできない。何せここはロープの上だ。焦ろうものなら真っ逆様に落ちていってしまう。しかし焦らないわけにも行かない。このままのんびりしていても真っ逆様に落とされてしまう。しかもここはちょうどロープの真ん中なのだ。後戻りをするわけにも行かない。仕方がないので、少しだけ急いだペースで前に進もうとする。しかしたどり着くのが間に合ったとしても、この奇術師に突き落とされるような気がしてきた。しかしじっとしても居られない。意を決して前に進んでいくことに決めた。少しだけ急いだペースで。
ガクン
あぁ、腰が砕けるように、足下が崩れる。ロープは目の前でどんどんと解れていく。もうダメだ。そう思った時、宙に浮いた。ここは確か三階の高さだったなぁ。三階くらいだったら死なないよなぁ。場違いというか、そんなのんきなことを考えていた。体は宙を舞っていた。走馬燈が走る余裕もなさそうだ。時間はさらにゆっくりと流れている。しかし走馬燈が駆け抜けるだけの時間はなさそうだ。頭から落ちなければ助かるよなぁ。三階ってこんなに高かったっけなぁ。落ちた衝撃を感じないや。ひょっとしてもう死んでたりしてね。でも、確かに落ちている感触はあるんだよね。
6.奇術師
気がつくと、ベッドの上に寝かされていた。側には心配そうな顔で見ている先ほどの奇術師の顔があった。向こうには入り口で会った老人が居た。
「大丈夫ですか」
心配そうに奇術師が問いかけた。しばらく何がなんだかわからなくなっていたが、ふと冷静に戻ると、そもそもこの奇術師がロープから落としたのではないかと気づいた。しかしその奇術師が何故僕を心配そうに見ているのだろう。ところで、みんなは何処に行ってしまったのだろう。そもそも僕らは、この館で何をしていたんだ。何をしに来ていたのだっけ。いろんな事が頭の中を巡っていた。自分が今まで何を考えていろいろなことをしていたのかわからなくなっていた。このわけのわからない奇術師にも言いたいことは山ほどある様な気がするが、とにかくみんなの元へ帰ろう。そう思っていた。そして僕はそのベッドから起きあがった。
「あ、大丈夫だから。もう帰して下さい。それと、あなた方の奇術とやらには一銭の価値もありませんよ。だから僕は一円も置いていきませんよ。とにかく、出口はどっちですか」
そう一気にまくし立てて、僕は帰ろうとした。彼らの返事を待たなくてもこの部屋には一つしか扉がないようだった。とにかくその扉を出よう。そう思い、その扉の方へ進もうとした。そうすると、その奇術師が僕の腕をつかんできた。
「ちょっと待ってよ。もっと遊ぼうよ。せっかく来たんだし」
えぇ、先ほどまであんなに格好をつけてはなしていた奇術師の変わり様に混乱した。遊ぼうよと言われても、一体。だいたい今までのは何だったんだ。まぁ、遊んでいたと言えば遊んでいたんだよな。しかし、現に僕は殺されそうになったわけだし。
「お坊ちゃんは、遊び相手を捜しておいでなのですよ」
今まで口を開いていなかった老人が話す。奇術師の方はというとまだ僕の腕を放さない。どうやらよほど遊び相手になって欲しいらしい。そんな風にだだをこねられても、僕はどうしようもない。とりあえず帰らせてもらうことにしよう。
「もう帰らせて下さいよ。だいたい僕らは道に迷っただけなんだし」
そう言っても、まだ帰してくれる雰囲気にない。そして奇術師は話を続けようとする。
「そうだそうだ。最初に爪に灯を灯してたトリック教えて上げようか。ろうそくを手の中に持ってね。手の甲を相手側に見せるだけなんだ。ちょっとやってみるよ」
そう言うと奇術師は、部屋の隅の棚にある引き出しからろうそくとマッチを取り出した。そしてろうそくに火をつけて、手に握った。そしてその炎の部分だけが見えるように手の中に持ち、手の甲を僕の方に向けた。確かに僕らが始めに見た光景だった。考えてみると遠くの方から見せられてので、何となく爪に灯火が灯っているように見えたが、こんなに近くで見ると、明らかに不自然なのがよくわかる。
「そうそう、それからねぇ。最初にあったビリヤード場のトリックはねぇ。あの水晶玉には磁石が入っていて、台の下側にある磁石で動かしていたんだよ。で、人が手をかざしたらその熱に反応して台の下にある磁石が動くんだ。これで誰も、あの水晶玉にはさわれないという訳だよ」
あ、やっぱりそうか。なんだかトリックを明かされてみて、なるほどというよりはやっぱりかという感じがした。まぁ、それにしてもその熱センサーは異常に感度のいい熱センサーなんだな。ふつうあんな敏感には、反応しないと思うんだが。
「でもね、よくあのトリックを破ったねぇ。僕あのトリックを破られるとは思わなかったよ。その後の、プロジェクターなんて使う必要ないと思ってたんだけど。あれはやっぱりすぐにわかっちゃったみたいだね」
ほおって置いたらまだまだこの奇術師は話を続けるんだろう。そう思ったので言い返してやることにした。
「あんなトリック誰だって破れるだろう。君の奇術のショウという奴は面白くないんだよ。僕らは君の幼稚な奇術につきあってられないんだよ」
そういうと奇術師は泣きそうな顔で僕を見つめ返してきた。僕は言い過ぎたかな。そんな気がしたが、殺されそうになった僕がこれくらいのことを言うのは十分理にかなっているだろう。そう思ったので、そのまま帰ろうとした。そうしようとする僕に、老人が話しかけてくる。
7.脱出
「まぁ、聞いてやって下さい。お坊ちゃんは小さい頃からここで一人で暮らしてきているんです。まぁ、私が教育係として付き添ってはおりましたが、何しろ遊び相手になるには年寄り過ぎでしてなぁ」
なんだかよく話が分からない。だいたい、お坊ちゃんは、とはいっても目の前にいるのは大の大人ではないか。それにどうしてここで一人で暮らしてきているんだ。そんな疑問が、帰ると言うことしか頭になかった僕を引き留める。別に何も彼らの話を聞いてやる義理はないのだが、なんだか気になったのでとにかく話だけは聞いてみよう。そう思い、また腰を下ろす。
それから僕はしばらく、老人の話す奇術師の生い立ちに耳を傾けた。この奇術師は、もともと大金持ちの息子なのだそうだ。そしてその親がこの子をのびのびと育てるためにとこの屋敷を建てたらしい。しかし、その親は交通事故で死亡し・・・・。もういいだろう、要するに、この奇術師はここでひとりぼっちなのだ。そして、この隔離された社会で一人で生きている。考えてみればかわいそうな話だ。ふとそう思いそうになったが、別にそんなことはないだろう。だいたいお金はあるんだろうし、どうしてこの奇術師は社会に出ていかないのだ。社会に出ていくのに壁になるようなものは特にはないだろう。いとも簡単に当たり前の理屈にたどり着いた僕は、それを二人に告げてみた。
「うん、そうですなぁ。私も先代にお坊ちゃんの教育係としてここで面倒を見るように言われたままで、特にこの子をこの屋敷から巣立たせるようにとは聞かされていなかったものでしてなぁ。そう言えば別にここにずっと居なければならないと言う理由はありませんなぁ」
なんてのんびりとしている人たちなんだ。なんだかよくわからないが、人助けをした気分だ。なんだか疲れてきたので今度こそ本当に帰ろう。
「あ、そうだ。帰られるのなら、お坊ちゃんも一緒に連れていってやって下さい。急に一人で社会に出ていくと要っても不安も多いでしょうから、お願いします」
断るのももうしんどいので、いいですよ、と返事をして今度こそ本当に返してもらうことにする。
その部屋の扉をぬけると、玄関まではすぐだった。そしてそこにはみんなが居た。
「おいおい、何処に行っていたんだ。落ちていった先には、何かがひいてあったみたいだから、多分生きてはいると思っていたが。姿が見えないんで心配したんだぞ」
僕の顔を見ながら、恵太がそう言う。あぁそうか、今まで得には気にしなかったが、だから僕は生きていたのか。まぁ、とにかく帰ろう。そう思い、今まであったことをみんなに話した。そして奇術師をつれていくことにも同意を得た。
夢から覚めたような顔をして、僕らは車の中に乗り込んだ。また道に迷わないように、気をつけなければいけないな。そんなことを考えながらエンジンをかけて、さぁ帰ろう。否、むしろ現実に戻ろう、そんな言葉の方が似合うかも知れない。
「ごめん、僕さぁ、最初の廊下のせり上がる壁を出すタイミング遅らせちゃって。おかげで額ぶつけちゃったみたいだね。ほんと、ごめん」
奇術師は、祥子にそんなことを謝っている。そうか、まだ側に奇術師はいるんだった。まだまだ現実には戻してもらえないのかも知れないな。
※この作品は1999年7月24日から1999年8月5日の期間にこのホームページにて連載されました。