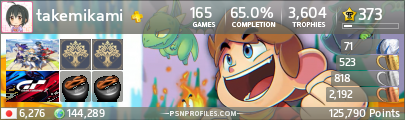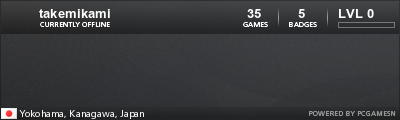Deadman Inside
重そうなスーツケースを抱えた男がホテルに足を踏み入れた。隣には女が居た。おそらく夫婦か、恋人同士か。二人にはこれといった特徴はない。あえて言うなら二人とも、そこそこいい男、そこそこいい女、だろうか。
二人はホテルにはいるとフロントに向かい、さっさとチェックインを済ませた。そしてベルボーイが二人に駆け寄り、「お荷物お持ちしましょうか?」と尋ねた。男は「あ、すいません」とベルボーイにスーツケースを渡した。「重い荷物ですね」とベルボーイが言うと、男は小さく言った。
「デッドマン・インサイド」
男のその言葉にベルボーイと女は沈黙した。それから女は取り繕う様に言った。「あっ彼、冗談好きなんですよ」女の言葉に続いて男は「いやぁ、特にブラックユーモアがねぇ。あはは、お恥ずかしい」ベルボーイは冷ややかながらも商売上の笑みを浮かべて、二人を部屋に誘導した。
それから、ホテルの一室で、男と女の二人だけの空間になった。
「あなた、どうしてあんなこと言うのよ」
女の言葉に対して、すまなさそうにスーツケースを開きながら男は答えた。
「いやぁすまない。俺嘘つけないんだよ」
男の開けたスーツケースの中には、バラバラになった男の死体があった。
「嘘つけないって、もしバレたらどうするつもりだったのよ」
「仕方がないだろう。俺は幼稚園の頃から両親に嘘をつかないようにって育てられてきたんだから」
「それにあのシチュエーションだったら、別に中身聞かれた訳じゃなかったんだから、わざわざ言わなくてもいいじゃない」
「まぁ、そうだけど。言いたかったんだよ、俺が死体運んでるんだぜって事をさ。なんかスパイ映画みたいで格好いいじゃないか。なかなかできる経験じゃないぜ、死体もってホテルに泊まるなんてさ」
「あのねぇ、だいたい死体の入ったスーツケースを拾ったからって、わざわざホテルに泊まりに来ないでよ」
「おまえだってついて来たじゃないか」
「まぁ、そうだけどね」
「そんなことはとりあえずさ。せっかくホテルに来たんだし、ゆっくりしていこうぜ。これから夜にもなることだしさ」
「その前にこの死体をどうするのよ」
「いやぁ、そんな者は二人の愛の前にはどうだって事はないさ」
「そんなこと言ってられないでしょう」
「せっかく雰囲気盛り上げようとしてるのに。あっそうだ、ルームサービスでも頼むとするか」
「いや、だからそんなことはどうでもよくってこの死体をどうするのよっ」
「うーん、困ったねぇ」
「あなた、ほんとに困ってるの?」
「おう、すっごく困ってるぜ」
「信じられない」
その言葉は完全に耳に入らないような顔をして男は言う。
「うーん、そうだなぁ。とりあえず考えてみよう」
しばらく二人は言葉も交わさずに、真剣に考えにふけっていた。
しばらくしてから、男はおもむろに立ち上がり言った。
「そうだ。本屋にでも行こう」
「うん、それでどうするの?」
「きっと『死体の入ったスーツケースを拾った時の対処の仕方』って本が売ってるはずだ」
「あのねぇ、死体の入ったスーツケースを拾った時はだいたいの人は、警察に届けるものなの」
「うーん、それも考えたんだけどさぁ。あの交番のお巡りさんがね。俺の嫌いだった小学校の先生にそっくりだったんだ」
「それで、警察に行かなかったの?」
「まぁ、そんなところかな」
「110番通報すれば良かったんじゃないの」
「うーん、それなんだけどさ。俺、小学校の時にいたずらで110番通報したら、親にこっぴどく叱られてさぁ。それ以来110番するのが怖いんだよ」
「はぁ、もういいわ。とりあえず、これからどうするつもりなの」
「うーん。どうしようかなぁ」
「頼りにならないわねぇ」
「あんまり先のこと考えてなかったからなぁ」
「あなたって、ほんとに計画性ないんだから」
「そんなこと言わずにこれからどうするか、一緒に考えてくれよぉ」
「もう、こんなに頼りにならない人だとは思わなかったわ」
男は非常にまずいと思った。このままでは、愛想を尽かされる。そして男は思いきった決断をした。
「よし、今からこの男を組み立てよう。幸い部品は全部揃っているみたいだ。きちっと人間の形をしていれば、ちょっとぐらいグッタリしていても、誰も気づかないはずだ」
「うーんそうねぇ、やってみよっか。あたしパズルとか好きだし」
「よしやろう」
そう言うと二人は死体の部品をベッドの上に並べた。
「でもこれ、全部で8ピースくらいしかないわよ。もっと分解して1000ピースくらいにしてから組み立ててみない」
「うーん、君がそう言うなら」
そういうと二人は、死体を細かく分解し始めた。
「どうだこれで、1000位にはなっただろう」
「そうね、やっぱりこれくらいはないとパズルとして面白くないわ」
「よし始めるぞ」
それから二人は、とても楽しそうにパズルを楽しんだ。「このパーツその下じゃないか」「違うわよ、これだったら左右が逆じゃない」「あぁそうか、じゃあこっちの下かぁ」という会話も時々聞こえ、二人は最高に幸せな時間を過ごしているように見えた。
「できたぁ」
女の嬉しそうな声とともに、死体が完成した。その死体は血色もよくとても死体には見えなかった。そして死体は歩き始めた。とりあえずバスルームに入って顔を洗った。
「いやぁ、すいませんな。わざわざ組み立ててもらっちゃって」
「そんなことないですよ。こちらこそ楽しませてもらっちゃって」
女は何の抵抗もなく死体と話している。男はとても混乱している様子だったが、はっとして、まだ死体が全裸であることに気がついた。
「おい、とりあえず貴様、そこにあるバスローブでも着とけ」
その言葉に女が反応した。
「別にいいじゃない。あたし達今までさんざんこの死体の体触ってたんだし」
「いやぁ、そうだがあれはバラバラだったし」
そうしていると死体は女に言った。
「かばってもらちゃってすいません。お詫びに夕食でもご一緒しませんか」
男は
「ちょっと待て、死体のくせに人の女を口説くな」
その言葉に女は
「別にいいじゃない。なんだかあたし、生きてる人に飽きちゃったの。あたしこの人について行くわ」
「ちょっと待ってくれ。そんな男の何処がいいって言うんだ」
「あら、この人だったら、分解して押し入れに片づけることができるのよ」
「うーん、それは俺には真似できんな。しかしそれだけじゃないか」
「分解できるって事は、組み立てる楽しみもできるって事じゃない。この人と一緒にいれば、いくらでもパズルが楽しめるわ」
「うーん、それも俺には無理だなぁ。しかしだなぁ」
しばらく男は黙り込んだ。そして
「うん、わかった。俺には勝ち目がないみたいだ。潔く身を引こう」
男は潔く飛び出していった。しかしその目には涙があった。
※この作品は甲南大学文化会文学研究会刊「ゲゲーベン40号」(1998)に掲載されました。