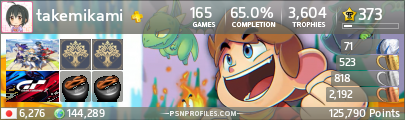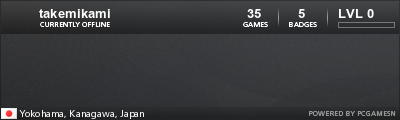銀河英雄伝説3 雌伏篇
この巻では、イゼルローン回廊における帝国と同盟の一進一退が描かれ続けられていただけで結局変化がなかったというのは文中にもある通りだが、もっとヤン・ウェンリーに言わすのなら歴史なんて結局同様のことが繰り返されるだけで変化のないものだと言いそうなものだと感じた。ここに来て、ユリアンがその頭角を現してきた。今まだユリアンというのは能力がありそうではあるが、話し安らぎを与えるために存在したような人物だった。それが、戦略の鬼と化していくのは寂しいような感じも受けたが、その戦略部分がこの話の面白さの大きな位置を占めているという事実があって複雑な感じを受ける。しかし、この巻の後半部に来てユリアンの安らぎを与える部分がかいま見れたので安心したという面もあった。今までの巻にも言えることだが、最後の部分で次の巻への不安をかき立てている部分が上手いなと感じる。