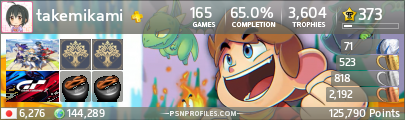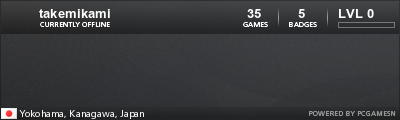理由付け
「時々思うんだよね。」
「何を?」
「何のために、これをやっているのかなって。物事に対する理由付けが欲しいというか」
静かな夜。
夜は静かなものだと決めつけてしまえば、静かな夜で良い。眠ろうと思っても眠れなくて、目が覚めた時。それは静かな夜で良い。
この夜は、眠りたいけれど眠ってはいけない夜。静かな夜ではない。しなければならない仕事がある夜。
窓の外は、その仕事を応援するように、明るい光が散らかっている。
哲也の夜は長く、朝まで眠ることは出来ない。もう殆ど決まっている。彼の仕事はコンピュータゲームを作ること、プログラマーだ。今時のコンピュータゲームはハリウッド映画ばりの莫大な予算を掛けて作ることが一般的だ。けれど、彼の作りたいゲームはそのようなゲームでは無い、ちょっとしたアイデアを上手く形にしてみんなを楽しませる。そんなゲームでみんなを楽しませたい、そんな思いからゲームのプログラマーになったのだ。
哲也の夜は続く。そんな思いとは裏腹に、彼はハリウッド映画ばりの巨大プロジェクトの末端にいる。単に期日までに言われたプログラムを言われたとおりに書くだけ、工場のラインの上に立って、基盤の上に部品を接着することを繰り返す。そんなイメージの仕事を想像してもらえばいい。そんな立場のままで、彼の思いは空回りを続けている。そんな哲也の夜はつづく。明日の朝までに、決められた事を決められたとおりに、作らなければならない。
哲也はずっとPCに向かったまま仕事を続けている。彼の席から少し離れた席には、環境のためのPCモニターが置いてある。決して眺めていて楽しいものではなく、ニュース速報の文字や会社の業績状況の文字がただただ流れている。殺風景。彼がいる場所はそんな場所で、他の場所に目を移せば、カップラーメンの柄やスナック菓子の袋が無造作に散らかっている。部屋の端っこに置かれたソファーには、汚れた毛布が転がっている。哲也は、朝、会社に来てここで仮眠をとっている同僚を何度も見ている。そして、哲也自身もそこで何度も仮眠を取っている。
「そろそろ帰るけど」
と、哲也の同僚が声を掛けてきた。彼が帰ると、哲也はこのオフィスで一人になる。
哲也は顔も上げず、PCに向かったまま声を返した。
「あ、はーい。お疲れ様でーす。」
それに続いて同僚が、環境のためのPCモニターを指さして聞いてくる。
「これ、電源落としておこうか?」
「どっちでも良いですよ」
哲也は相変わらず、顔もあげずにそのまま声を返した。
帰宅前の同僚は、「そっか、じゃあ」と良いながら、そのモニターに繋いであるPCをさわり始めた。PCのモニター画面が一度真っ暗になる。その後、水槽の中の映像がモニターに表示される。水槽の中には魚が2匹泳いでいる。これで、オフィスに水槽を置いた気分になれる。
「一人になった時、結構やっているんだよね。ここ、余りにも殺風景だから。じゃ、お先に。」
そういって、同僚は部屋を後にした。哲也は一人になった。モニターには、2匹の魚が楽しそうに泳いでいる。
カタカタという音が響く。ただ、その音だけ。天井を見上げる動作、時々口から漏れる独り言。
100%では無い静寂。そんな時間がしばらく続いた。
ガタガタッ、ガタガタッ。
ハッと気付いたように、哲也の目線が脇机に置いたケータイの方を向く。PCへの没頭からビックリした感じで。ケータイの発信元には「美希」の名前が表示されている。手をキーボードから離し、ケータイを開く。
「はい。」
「仕事中?」
「うん、今日は朝まで帰れない予定」
「大変そうね。」
「ちょっと、そっち行くね。どうせ、また晩御飯食べてないんでしょ」
「うん、そんな感じ」
「ふふっ、じゃまたね」
哲也はケータイを元に戻し、大きく伸びをした。首を左右に振り、溜息を一つ。また、キーボードに手を戻す。
電話の相手は「美希」と言う名前で哲也の恋人だ。もう2年程付き合っている。哲也が朝まで仕事で帰れない時には、よく差し入れを持ってオフィスにやって来る。プログラマーという職業からくる小難しい哲也の話も、笑顔で聞くことが出来る。哲也にとっては一緒に話をしていて楽しい相手だ。美希がその話の内容を理解出来ているかは別にして、彼は彼女に小難しい話をすることが好きだった。
カチャ。
「こっそり」という形容詞が似合いそうな勢いでオフィスの扉が開いた。扉の隙間から美希の顔が覗き、哲也を見つける。哲也を見つけたきっかけでその表情が笑顔に変わる。パタパタと哲也に近づき、肩の辺りを小突く。
「ちょっと休憩しよ」
美希はそう言いながら、ミスタードーナツの箱を持ち上げ、哲也の視線の先に合わせる。
「ミスタードーナツのおみやげ。晩御飯食べてないでしょ?」
「晩御飯にミスタードーナツは無いだろ」
「ほらほら、哲也の好きなフレンチクルーラーもあるし」
美希はそう言いながら、ミスタードーナツの箱を開け、部屋の隅っこに置かれたソファーに哲也を導いていく。結局彼女がオマケをもらうためのポイントを集めたかっただけと言うことを白状させながら、哲也はソファーに連れて行かれる。
ミスタードーナツの晩御飯を食べながら、他愛もない話を続ける。相変わらず残業が多いとか、友達が結婚したとか、そんな話。
「時々思うんだよね。」
「何を?」
「何のために、これをやっているのかなって。物事に対する理由付けが欲しいというか」
哲也が何を思って、この仕事をやっているのか。ちょっとしたアイデアを上手く形にしてみんなを楽しませたい。彼がそんな思いで、この仕事をしていると、何度も美希に話をしていた。美希は不思議そうな顔をしながら、いつも哲也から聞いていた彼の思いを、そのまま彼に答えた。
哲也は、ひとつ頷いて話を続ける。
「でも、どうして僕が『みんなを楽しませたい』と思っているのかそこに理由付けがないような気がするんだ」
「そこにも理由付けが必要なの?」
「これから朝までかけてしなければならない仕事は、巨大プロジェクトの末端。言われたことを言われた通りにやるだけのくだらない仕事なんだ。気は進まないけど、そんな仕事もやらなければならない。そのためには、もっともっと深い理由付けがないと辛いんだよね」
哲也の表情も、言い方も淡泊なままだった。しかし、哲也がこのような弱音を吐くのは珍しい、美希はそのように思い、力づけることが出来ないかと言葉を探した。
「ねぇ、この世に聖書の物語がある理由って何だと思う?」
その美希の言葉に、哲也は迷ったような表情をした。このような小難しい話はいつも哲也の方からするし、美希はそれ聞くと言うのがいつものパターンだった。
「この世に聖書の物語が必要な理由は、『理由付け』なんだと思うの。この世界の始まりって、現代の科学でもはっきりしないわけでしょ。この世界の始まりとかこの世界が存在する理由とかって、誰かが決めてしまわないと仕方がない。だからこの世に、聖書の物語が必要になったんだと思うの」
哲也の迷った様な表情、びっくりした表情はそのままで、美希は更に言葉を続ける。
「だから、理由付けって決めてしまわないと仕方がない。哲也が『みんなを楽しませたい』と思ってそう決めたのであれば、それを信じて欲しいの。応援するから。」
哲也は美希が励まそうという思いに気付き笑顔を返す。
「有り難う、そうだね」
「でしょ。だからあたしは、『オマケをもらうため』と言う理由付けをしてミスタードーナツを買ってきたの。納得でしょ。」
哲也と美希は顔を見合わせて笑い合う。
少し離れたPCモニターの水槽でも魚同士が顔を合わせて笑い合う。
「僕たちが存在する理由付けは簡単だよね」
「そう、『鑑賞されるため』だもんね」