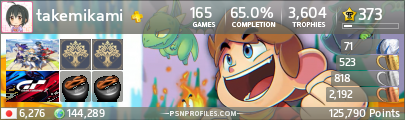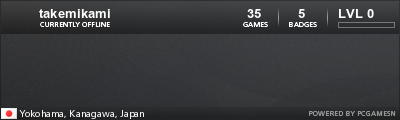二論者・一聴者
私は酒席にいた。そこには、私の二人の友人「Y」と「S」が同席していた。私たちは、何気ない会話を進めていた。酒もだいぶん入って二人は少し興奮した状態で会話を続けた。友人をけなすようだが、二人ともなかなか賢い男だと思うが、言い出すと譲らないのが玉に瑕でよく口論をするのだ。今日も例に漏れずその雰囲気に突入しようとしている。
「どうだろう。例えば、君の側にいる友人がこれから人を十人殺そうとしているとしよう。君はこの友人が犯罪を犯すのを黙ってみては居ないだろう。きっと何らかの方法で止めようとするに違いない。しかしどうしても止められない時の最終手段はその友人を殺してしまい、十人の命を救うことだろう。」
Yはそう言ってコップのビールを口に流し込んだ。
「君はどこかの宗教の代表者のようなことを言うんだな。その考え方も一理あるだろう。しかし、その考えには大きな欠点があることに気がつかないかなぁ。最終手段と言うけれど何処が最終なんだい。最終なんてものはないだろう。そのように考える時は、きっと人間の本能の中にある「殺人欲」というものが働いて、自分が人を殺す大義名分を自分に突きつけて納得しているだけなんだと思うよ。」
落ち着いた口調のSが話し終えると、Yの反論が始まった。
「最終が何処かとかそういう問題じゃあない。S、君のように考えていて何もしないことが一番罪なんだ。傍観していることは一番楽だし、言い逃れもし易い。君のように傍観を決め込む奴が多いから、シカトといういじめができたりするんだ。とりわけ、僕の言ったケースは、自分の友人が犯罪を犯しそうになるといったケースだ。この場合は友人の為にも、殺してしまうぐらいの関わりをする方が正義だと思わないか。」
オーバーなジェスチャーを加えての反論だった。それからの二人の会話は、おおかた「何処に何処まで関わるのが正しいか」ということでまとめられると思う。私はあまり達者に弁論できる人間ではないので、二人の口論を聞いているだけだった。
そんな時、Sが席を立った。どこかに電話をかけなければいけないらしい。すると、おわかりだろうが、残されたのはYと私の二人だけだ。やはり、Yの会話の矛先は私に向いてくるのだ。
「君はずっと黙って居るみたいだけど、どう思う。自分の友人なんだから、最後まで関わっていくのが正しいだろう。そう思うよなぁ。」
Yの言い方には迫力がある。思わず何も考えずに「はい」と答えてしまいそうになる。
「だけど、殺してしまうのはどうかなぁ。」
そんな、私自身情けないと思わざるを得ない、幼稚な答えをしてしまった。
「君は殺す手前まで関われ、と言うんだね。それは苦しいよ。最後の最後で友人を見放してしまうことになるんだ。君はきっと、殺人をする罪以上に重い苦しい罪を背負って生きていかなければならなくなるんだ。」
何も言えなかった。言えなくなってしまった。Yはこんな私を傍観者と呼ぶだろう。私は、何もしない罪な人間ということになってしまうのか。とにかく、紛らわすつもりで、適当に酒の当てに手を伸ばしておいた。
Sが戻ってきたのは数分後だった。私はSが戻ってきてくれたのが非常にうれしかった。あのままでは、自分が無責任な傍観者である罪に苦しみ続けるところだった。しかし、Sが口を開けて出した言葉には苦しめさせられた。
「僕が居ない間にYにいろいろ言われただろう。僕の言い分もいろいろ聞いただろうから、君の意見を聞いてみたい。Yの考え方は極端だ。僕の考え方の方が理解できるだろう。何処まで関わるかということは関係ないことで、何処に関わるかなんだよ。つまり、Yの例で言う所では、直接に犯罪を止める観点で関わらずに、犯罪を止める手だてを尽くしていることができればいいという観点で関わるんだ。この場合、結果がどうかという事が問題じゃなく、尽くしたか尽くしていないかが問題だ。自分が納得することが問題なんだ。」
なんだか混乱してきた。どちらの言っていることも、正しいようでもあり、間違っているようでもある感じがする。でもここで、何も言えなければ、Yの目に傍観者と映る。何も言おうとしなければ、Sの目には関わることもできない者と映る。だから私は言ってやった。
「二人の言っていることは、一理はあるけれど、一理しかない。」
YとSは、話題を女の話へと移していった。