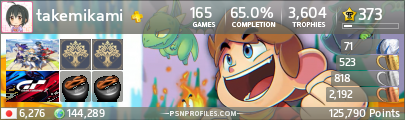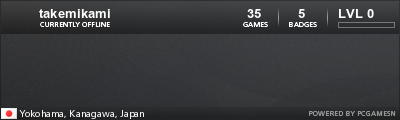ボヘミアンガラス・ストリート 4 ランデブー
いよいよ決断が実行されようとしている、そんな光景がこの巻においてに見られた。この小説が恋愛小説であるということがある上で、そこから起こった事実からの決断を迫られる。しかし迫られたといっても、迫ったのは自分だということがそこにある。ほとんど決断を迫られるということは、自分で迫っているということだ。これが余りにも当たり前だということは、言うまでもないと思う。しかし、自分がいつもそんなことで被害者の気分になっていることも、言うまでもない事実だった。
それから、俗的なことだけど、心情の描写を生理的に表すことが余りにもくどいように感じた。