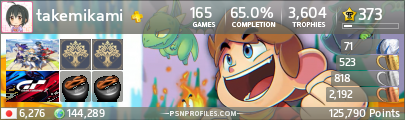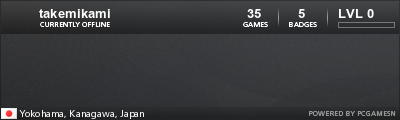野火
文学研究会の後輩から、龍谷大学の読書会でこの本を取り上げると聞き、この本を手に取った。この作品は、フィリピン戦線で結核を患って本隊から追放された敗戦兵が、孤独の中で生き延びるようとする物語だ。生き延びようとする過程で、何の罪もない一般人を射殺し悔い悩む場面や、「私が死んだら、ここの肉を食べてもいいよ」と漏らした友軍の言葉を受けて人を食らって良いものかと悩む場面などがとても印象的だった。
随分と以前の話になるが、うちの部の後輩が「死ぬ」の反対である「生きる」を作品に書くのは難しいといっていたが、やはりこの作品でも死を描くことで生を表現していた。戦争というと、やはり生と死を描くものなのだろう。
この作品を読んで、何となく「ビルマの竪琴」とかをもう一度読んでみようかなという感じがした。特にこれといった理由もないんだけれど。